- 【オネイロス】第1話 選抜① 2025年9月4日




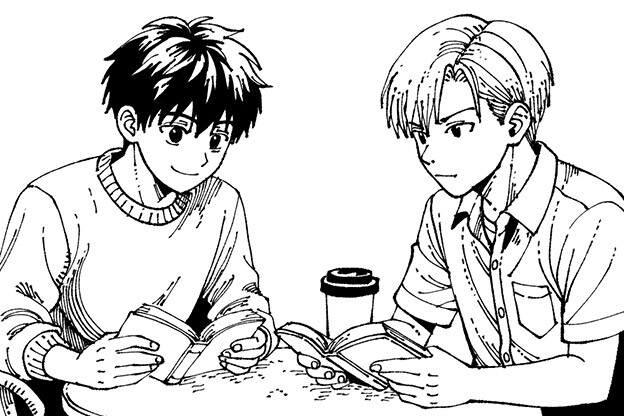
地球は、もはや見えない侵略者たちの巣窟となっていた。
その正体は、目に見えない形で人間の意識を乗っ取る宇宙人。
彼らは日常に溶け込み、地球人として振る舞いながら、確実にその数を増やしていく。
僕は唯一の例外だった。
“地球人としての意識”を保っているのは、どうやら僕一人らしい。
しかし、この事実を誰かに知られてはいけない。
もし知られたら、僕も彼らの仲間にされるか、最悪の場合、命すら危うい。
僕にはずっと、周囲の誰ともわかり合えないという感覚があった。それは昔からのことで、たぶん僕自身に問題があるのだろうけど、僕はその孤独を“地球が侵略されたせい”にしていた。
僕がその孤独を紛らわせる手段は、本を読むことだった。
誰にも理解されないなら、せめて誰かの書いた物語の中でなら、自分を見失わずにいられる。
活字の世界にいるあいだだけは、侵略されずに済むと信じていた。
僕は、シオドア・スタージョンの『夢見る宝石』や、フレドリック・ブラウン、レイ・ブラッドベリなど黄金時代のSF小説に耽溺していた。
それらの物語は、時に現実からの逃避であり、また僕の現実そのものを映す鏡のようでもあった。
異星人、奇妙な世界、そして孤独。
それらは僕の心の中に強く響いた。
もしかしたら自分が地球に馴染めないのは周囲がみんな宇宙人だからなのではないかと、僕は考えるようになっていた。
そんなある日、学校の図書室で僕は隣のクラスの餅郎に出会った。
彼はハインラインの『人形つかい』を読んでいた。
僕ももちろん夢中になった、地球外から飛来した異生物によって人間を操られる侵略テーマの小説だ。
彼がその本を読んでいたというだけで、僕は勝手なことだけど希望を見出してしまった。
“きっと、この人なら通じ合えるかもしれない”と。
僕は勇気を出して声をかけた。
「それ、好きなのか?」
餅郎は少し驚いた顔をしたが、すぐに穏やかに笑った。
「ああ、いいだろこれ。こういう話、好きなんだ」
その一言で、僕たちは一気に意気投合した。
僕たちは図書室の隅で何時間も話し込んだ。
餅郎もまた孤独な時間を本の中で過ごしてきたという。
彼はスタージョンやブラウンの話題にも詳しく、僕たちはお気に入りのシーンについて語り合った。
「ブラッドベリの『万華鏡』、読んだことある?」
僕が聞くと、餅郎は熱心にうなずいた。
「あるとも。あの宇宙飛行士たちが漂流する話だろ。切ないよな……でも美しい」
「だよな」
僕は心の中で何かが満たされていくのを感じた。
僕たちはその後も、放課後や週末を図書室やカフェで過ごした。
本の話だけではなく、世界がどう狂っているか、自分たちの周りの人間がどれだけ奇妙に見えるか、そんなことも話題に上った。
孤独な読書家だった僕たちは、いつしか互いを心の拠り所にしていた。
「なあ、君も思うだろ?」
ある日、僕は思い切って聞いた。
「周りはみんな宇宙人なんじゃないかって」
餅郎は真剣な顔でうなずいた。
「そうだ。俺も気づいてる。周りの奴らが変だってことに」
僕たちは、それからますます強く結びついていった。夜遅くまで話し込み、時には一緒に街をさまよいながら、見えない敵に立ち向かう方法を模索した。
最近、街が少しだけ違って見えるようになっていた。
色が鮮やかに感じられる日が増え、誰かと話すのがほんの少しだけ楽になっていた。
……僕が〝地球人でなくなってきている〟かもしれない?
そんな疑問を振り払うように、また本に手を伸ばす。
ある日、僕たちは小さなカフェで食事をしていた。
話題はヤングの『ジョナサンと宇宙クジラ』だった。二人ともその小説に深い感銘を受けていたが、解釈について意見が食い違った。
「いや、ジョナサンはクジラに同化されるんじゃなくて、あれは心が繋がることの象徴だろ」
僕はそう主張した。
「違う。あれは完全な支配だ。クジラの方が優れていて、ジョナサンはそれを受け入れざるを得なかったんだ」
餅郎が反論した。
「いや、それはおかしいだろ!ジョナサンは最後まで自由を失ってない」
「お前、何も分かってないな。本当に読んだのか?」
餅郎の声が荒くなる。
「読んだから言ってるんだ!」
僕もつい声を荒げた。
「お前、その解釈、どう考えても地球人らしくないだろ!」
「何だと?餅郎、お前こそおかしいぞ!」
「こんなこと言いたくないけれど……」
餅郎は上目遣いで僕を睨んだ。
「俺は見たんだ、お前が教室で誰か女と楽しそうに喋ってんのを」
僕は動揺した。
たしかに僕は最近、席替えで隣席になった千真希と話すようになった。
ちょっと仲良くなっただけで、それ以上でも以下でもない。
彼女だって宇宙人だ。僕が心を許すはずがない。
でも心の奥底で少し嬉しい感情があったことも確かだ。
そのことを餅郎に知られたくなくて黙っていた。
ひょっとして、餅郎は僕の変化を気づいているのか?
餅郎は小声だがきっぱり言った。
「お前は宇宙人なんだろ?」
その瞬間、僕たちの間にあった信頼は音を立てて崩れた。
数分後、僕たちは無言で席を立ち、それぞれ別の方向へと歩き出した。
夜の街を歩きながら、餅郎の言葉が頭の中でこだました。
「お前は宇宙人なんだろ?」
僕の起こった変化は、知らぬ間にすこしずつ宇宙人の支配下に置かれたからなのだろうか。
千真希と話すことで芽生えた、ほんの小さな安心……それが宇宙人に支配されたというのなら、僕たちの思っていた地球人らしさとは。
こだまする声を振り払うことができない。
餅郎と千真希……地球人と宇宙人の狭間で、僕はどちらに向かって歩を踏み出すべきか……答えを求めてさまよい続ける。
宇宙人が行き交う地球の底で。
—— おわり——

深夜、突然ドアが激しく叩かれた。
ドンドンドン!
「ねえちょっと開けてよ!」
聞き覚えのある声。それも、今ここにいるはずのない人物の声だった。
俺は戸惑いつつも玄関に向かい、ゆっくりと鍵を開ける。するとドアの隙間から勢いよくねり奈がなだれ込んできた。
「何で鍵変えてんのよ、頭おかしいんじゃない?」
玄関の明かりを受け、酔いか怒りか真っ赤になった顔でこちらを睨む。
「お前と俺は別れたんだよ」
「何バカなこと言ってんのよ〜」
どうやら酔っ払って、別れたことを忘れて俺の家に帰ってきたみたいだ。
こういうところが可愛くて好きだったんだが……
ねり奈は靴を脱ぎ捨て、そのままキッチンへと歩いて行った。勝手知ったる我が家、といった様子で冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出し、一気に喉に流し込む。水を飲み干し、一息つくと、少しずつ彼女の目に正気が戻っていった。
「朝、喧嘩したっけ? そんなことずっと引きずっているから駄目なんだよ」
「いやいやいや……離婚したじゃん。一年前に」
俺がそう告げると、ねり奈は眉をしかめた。
「何バカなこと言ってんのよ」
「バカじゃないよ。二〇二四年の四月二六日、俺の誕生日に離婚したから覚えてる」
「二〇二四年の四月二六日? 明日じゃないの。今日は二五日だよ!」
ねり奈は呆れた顔でスマホの画面をこちらに突きつける。日付表示は、確かに『二〇二四年四月二五日』になっていた。
「ええっ」
思わず、俺も自分のスマホを取り出し、彼女の目の前に差し出した。
「今日は二〇二五年三月二三日だぞ。お前のスマホの時間表示はおかしい」
「今年は二〇二四年だよ!」
「いや二〇二五年だ」
ねり奈と俺は黙ってお互い見つめ合った。
あいつは、嘘をついている様子はない。
ねり奈は周囲を見渡し、何かに気がついた。
「私の荷物は?」
「ああ、お前が離婚した次の日に運送会社に頼んで実家に送ったじゃん」
「ちょっと待って、ちょっと待って……」
ねり奈は片手で頭を押さえ、深刻そうな顔で考え込む。さすがに酔いは完全に覚めたらしい。
「帰ってくる途中……バスを降りて歩いていたら、突然、視界がぐんにゃり歪んで、一瞬気を失ったの。そのときは、自分でも酔っぱらいすぎだって思ったけど……」
真剣な表情のまま、とんでもないことを口にした。
「私、時空を超える……ワームホールみたいなものを通っちゃったのかもしれない」
ありえない仮説を出して自分自身を納得させようとする。その姿勢もねり奈らしい。
沈黙のあと、ねり奈は唐突に叫んだ。
「何で別れたの!」
「お前がいきなり別れようって言ったんだろ!」
思わず声が大きくなった。
「あの日、朝に口論して帰ってきてすぐそれだったから、俺だってびっくりしたんだよ……」
俺はため息をついた。
「次の日には仕方なく離婚届を取りに行って、書いて、判子を押した」
「私と別れたかったの?」
真っ直ぐな視線を向けてくる。
「そりゃ別れたくなかったけど……」
その言葉を聞いたねり奈は、さらに声を荒げた。
「もっと説得しなよ! 本当に好きなら、別れたくないって。あんたのそういう、本当の気持ちを秘めて我慢するところがイヤなんだよ!」
「いやいやいや……相手がいやだって言ってるのに説得したら、それは強要になるだろ?」
「そういうところが駄目なの! 私が理不尽なことを言っても、我慢して我慢して……ああもう、うじうじしたところがイヤ!」
「やっぱりイヤなんじゃないか」
「イヤじゃないよ! 別れたくないなら別れたくないって意思を通さないから別れたんだろ!」
ねり奈は、ふと素の顔に戻り、小さく問いかける。
「あんたの時間の……現在の私は、今どうしてんの?」
「俺と別れて二ヶ月後には彼氏ができたとかで、今はその男と同棲してるよ」
ねり奈は、それを聞いてニヤリと笑った。
「さすが私、もてるな〜」
自分で褒めるその無邪気さが、たまらなく可愛いと思った。
ねり奈は真顔になって、俺の顔をじっと覗き込む。
「あんたは今も私のこと好きなんでしょ?」
「そりゃ好きさ」
「そうよねえ、あんたはもてないし私一筋だったもんね」
そのまま俺の頬を手で挟み込み、強引に顔を近づける。
「今度私が別れたいって言っても、絶対別れたくないって言え!」
「う、うん……」
「ちゃんと約束しろ!」
「別れたくないけど……君はもう新しい彼氏が……」
「それは別の私だろ。本当の私、この私とだよ!」
「別れたくない」
「そんなんじゃ駄目!」
「別れたくないっ!」
「もう一度!」
「別れたくないっ!」
俺は腹の底から絶叫した。
「そうだよ、その気持ちだよ! 今後、何があっても、私が癇癪起こして別れ話を始めても、絶対に別れちゃ駄目だよ。君は君の気持ちを大切にしないと駄目!」
勝手なことを真剣な表情で言う。だが、そこが好きだったのだ。
「絶対に別れちゃ……」
その言葉の途中で、ねり奈の輪郭がぐんにゃりと歪んだ。ぼんやりとした渦のようなものが彼女を包み、淡く光を帯びて、彼女の姿はそのまま静かに掻き消えた。
ワームホールって、本当にあんな感じなのかもしれない。
俺はねり奈からもらった勇気に背を押され、思い切って電話した。
ねり奈はすぐに出た。
「何? こんな時刻に」
猛烈に不機嫌そうなねり奈の声が響く。
「横で彼氏寝てるんだけど」
「今……君が来たよ。一年前の君が」
「え」
ねり奈は絶句した後、静かに続けた。
「そっか、じゃあ今だったんだ」
「知っているのか?」
「覚えてるよ。一年前のことだもの。あの後、気づいたら最初気を失った場所に私また立ってたんだよ」
「じゃあ、わかっているよね」
「何が?」
「僕は君と別れたくない」
「おそっ!」
ねり奈が怒鳴った。
「あの後帰ってすぐ、君に『別れたい』って言ったら『うん、わかった』って即答だよ! 君からすれば朝言い争いしたから、その夜にあり得たことかもしれないけど、私からすれば、そんなに好きじゃなかったことかなって思うよ! 直前に『別れたくない!』ってあんなに叫んでいたのにさ」
「いやいや、それは一年後の俺で……」
「そうやって言い訳するところがイヤ!」
もう滅茶苦茶だ。
「もう遅い! バイバイ! 二度と電話しないでね!」
プツッ!
こういう勝手なところが好きだったんだよな〜。
俺は泣き笑いの表情でスマホを見つめていた。
——おわり——

岡市たかし(おかし たかし)がダンプに跳ねられ命を落としてから半年が経った。
納棺の際、母親の岡市多辺美(おかし たべみ)はたかしの部屋に入り遺品を探した。
本棚には、たかしが大切にしていた漫画がぎっしり詰まっていた。
異世界転生をテーマにしたものばかりで、主人公が圧倒的な力を手にし、仲間たちに崇められながら美少女たちと幸せに暮らすという内容だった。
「現実のたかしとはまったく正反対ね……これが、たかしの求めていた世界だったのね」
多辺美は泣きながら目立つ場所に置いてあった本を棺の中に入れた。
「だから、たかしはその理想の世界へ旅立ったのね……きっと異世界で幸せに暮らしていることでしょう。こっちの世界で幸せにしてあげられなくてごめんね……」
葬儀屋が棺の蓋を閉じ、たかしが多辺美の息子として生きた日々は幕を閉じた。
ある日、多辺美はたかしの遺品の一つであるゲームを手にした。
それは異世界を舞台にしたRPGだった。
たかしが途中で放置していたデータを開いてみると、メイキングで作られた主人公の顔がたかしにそっくりだった。
「まあ、このゲーム、女性キャラクターばかり仲間になるのね。それに主人公だけが圧倒的に強いなんて、バランスも何もあったものじゃないわ」
ゲームの中では、たかしそっくりの主人公が剣を握り、異世界を駆け回っていた。
光る剣を振りかざし、巨大な魔物を次々と倒していく姿は、現実のたかしとはかけ離れた頼もしさだった。
たかしの冒険には、美少女の仲間たちがずらりと並んでいた。
それぞれが個性的で可愛らしく、主人公を敬愛してやまない彼女たちの姿を見て、多辺美は少しだけくすりと笑った。
「こんな世界に憧れていたのね……」
たかしが生前に見せていた無口で大人しい一面からは想像もつかないようなゲームの世界観だったが、多辺美はそのギャップがどこか愛おしく感じられた。
最初は慣れないゲームの操作に戸惑いながらも、多辺美は進めるうちに主人公と旅する女性キャラクター名を変更できることに気づいた。
「『たかしママ』……これでいいわね」
名前をつけられたキャラクターは、たかしの冒険に寄り添う回復役のサポートキャラだった。
「たかし、しっかり守ってね」
冗談交じりに画面越しの息子に語りかけると、その直後、たかしが画面の中でチート能力を発揮し、大勢の敵を一撃で蹴散らした。
「すごい……本当に頼もしいわね!」
多辺美は歓声を上げた。戦闘のたびに、たかしが彼女を守り、導く姿に多辺美は心を奪われていった。
どんな危機的状況でも彼が放つ一振りの剣は光り輝き、戦いの終わりには決まって彼の背中がまばゆく映った。
「こんなに強いたかしと一緒に旅をしているなんて、夢みたい……」
多辺美はふと、自分が言った言葉に気づいて胸を締め付けられるような思いに駆られた。
確かに夢ではない——現実のたかしは、もう戻らないのだ。
しかし旅をする時間だけは、たかしと再び繋がれたように思えた。
旅が進むにつれて、多辺美は次第に現実を忘れ、ゲームの世界に深く引き込まれていった。
森を抜け、広大な草原を渡り、崖の上から絶景を見下ろしたとき、多辺美は画面越しでありながら心から感動した。
「こんな景色、たかしと一緒に見られるなんてね」
チラとたかしが少し振り返るように見えたのは、多辺美の気のせいだろうか。
時折、美少女たちが会話の中で主人公を褒め称えるのが耳に入るたびに、多辺美は少し照れくさくなりながらも嬉しく感じていた。
「たかし、こんなにみんなに慕われて……本当によかったわね」
そんな楽しい日々が続く中、旅の物語はついに大きな山場を迎えた。
それは、伝説のドラゴンが現れるというイベントだった。
画面いっぱいに映るドラゴンの姿は恐ろしく、多辺美は一瞬、手が震えた。
「こんなの、倒せるの……?」
恐怖で動けないたかしママを守るため、たかしは真っ先にドラゴンに立ち向かった。
放たれる巨大な火炎もものともせず、剣を振りかざして攻撃を繰り出すたかしの姿は、これまで以上に輝いて見えた。
「たかし! 頑張って! かーちゃんも一緒に戦うから!」
多辺美も慌ててボタンを押して回復魔法をかけたが、ドラゴンの攻撃は容赦なくたかしを襲う。
何度目かの激しい突風の中で、たかしは吹き飛ばされ、地面に叩きつけられた。
「たかし! ダメ! あなたがそんなことをしたら……!」
多辺美の叫び声が響く中、画面の中のたかしがゆっくりと顔を上げた。
その目は、どこか懐かしさを感じさせるもので——いつの間にか、彼は現実のたかしそのものの姿になっていた。
「かーちゃん、大丈夫か?」
その声は紛れもなく、息子の声だった。
「たかし!?」
多辺美は画面の前で息を飲んだ。そこにいるのは、もうゲームのキャラクターではない。
本物のたかしが、画面越しにこちらを見つめている!
「かーちゃん、俺、異世界でも元気にやってるからさ。もう俺のことは心配しないで……かーちゃんには、かーちゃんの人生があるだろ?」
「何を言ってるの! あなたなしでどうやって生きていけというの!」
涙を流しながら訴える多辺美に、たかしは優しく微笑んだ。
「俺、かーちゃんの子供に生まれて、本当に幸せだったよ。異世界転生しても絶対かーちゃんの子供になりたい……今まで、本当にありがとう」
たかしはドラゴンに向かって剣を振った。チート能力で一閃、ドラゴンは倒れた。
そしてゆっくりと立ち上がり、彼方へ歩き出した。
その背中を追いかけるように、多辺美は叫んだ。
「たかし! 行かないで! たかし!」
たかしは振り返らなかった。
遠くで待っていた旅芸人の女性と手を取り合い、やがて視界から消えていった。
多辺美は泣きながらリセットボタンを押し、セーブデータからやり直そうとした。
しかし、データは消えていた。
ゲームを最初からやり直してみても、あのシーンを見ることができなかった。
「あれは……幻だったの……?」
多辺美は呆然としながらも、真っ暗な部屋で立ち上がって電気をつけた。
「……私も、頑張らなきゃ」
「これが、小説投稿サイトで大人気の『たかしママ』先生が異世界転生ものを書き始めたきっかけです。息子さんの死を乗り越え、彼との絆を物語に託したのです」
数年後、そんなインタビュー記事が公開された。
—— おわり——

私は目を覚ます。
窓の外から差し込む光が、半分夢の中にいる私の意識をゆっくりと引き上げていく。
光とともに、世界が一気に広がっていくのが見える。
街並みや人々の姿、木々のざわめき。これらすべては、私が目覚めた瞬間に生まれたのだ。
そう、世界は私の想像の産物だ。
私が目覚めると同時にビッグバンが起き、宇宙が形作られる。
そんな壮大なスケールの中で、私はただの一人の人間として存在している。
でも、不思議なものだ。
私のために世界があるはずなのに、どうして私の人生はこんなにもうまくいかないんだろう。
眠りの余韻が消え、意識が覚醒するにつれて、部屋の中に光が差し込み、家具や壁が現れる。
窓の外の景色も徐々に「再生」されていく。遠くに見える電車、駅前の小さなコンビニ、通りを行き交う車や人。
「はいはい、おはようございます、私の世界」
心の中でぼんやり呟く。
鏡を見ると、寝癖のついた自分の顔がそこにある。この顔さえも、私が目覚めた瞬間に生成されたものかと思うと、妙な気分だ。
それにしても、もう少し綺麗な顔に生成してくれたらよかったのに。
高校時代、私は夢見た第一志望の高校に落ち、仕方なく第二希望の私立に通うことになった。
「唯一無二の私が志望校に落ちるって、何の冗談?」
大学だって、一浪してようやく滑り込んだ。
夢のキャンパスライフとは程遠い日々。
大富豪やアラブの石油王の娘だったら、何の苦労もなく過ごせたのに。
現実の父はしがない公務員。母も平凡な主婦。
家計はカツカツで、ファミレスのバイト代がなきゃ新しい服も買えない。
私の世界は私のために作られている——そのはずなのに、なぜ思い通りにならない?
「そういう風に作られているから仕方ないじゃん!」
心の中の誰かが呟くようにそう教えてくれるけど、納得なんてできない。
洗面所で顔を洗い、適当に食パンを齧りながらスマホをいじる。
ニュースを眺めていると、世界のあちこちで起きている事件や災害が流れてくる。
でも、ふと考える。これって本当に「実在」してるのかな?
私が見ていない場所なんて、実際はただの「未設定」なんじゃないだろうか。
ニュースに映っているのも、私が知り得ない遠い世界をもっともらしく見せるための「飾り」に過ぎない気がしてくる。
窓の外を見ると、やっぱり視界に入る部分だけがきちんと存在している。
もしかしたら、その先は映画のセットみたいに板を立てかけてあるだけかもしれない。
「この世界、どこまで本当なんだろう?」
そんなことを考えながらコートを羽織り、家を出る。
いつもの電車。いつもの景色。
駅前のパン屋の匂いも、通り過ぎる制服姿の高校生たちも、きっと「私が見ている間だけ」存在しているんだろう。
車窓の景色をぼんやり眺めながら、ふと考える。
「私が電車で眠っているとき、椅子の上に座ったまま虚空を並行移動しているのかな」
そう思うと怖くなる反面、どこかこっけいな気もする。
すべては一瞬一瞬、私に合わせて作られているのだから、未来のことを気にする必要なんてないかもしれない。
でも、その一方で、大学に着いたらまた嫌なことが待っているとわかっている。
それも私の想像だとしたら、どうしてこんな嫌なシナリオにしたのか、自分でも理解できない。
もっと楽しい大学生活を設定してもよかったんじゃないの?
講義室に着くと、相変わらず淡々とした時間が流れる。
退屈な講義を聞き流しながら、たまにノートを取り、スマホをいじる。
隣の席の子が何か話しかけてくるけど、適当に相槌を打つだけ。
世界が私の想像でしかないなら、きっとこの子も私の「脳内キャラクター」だ。
そう思うと少し気楽になれるけど、同時に寂しさも感じる。
夕方になるとファミレスのバイトへ向かう。
エプロンを付けてレジに立つと、今日もいつも通りの風景が広がる。
「いらっしゃいませー」
と声を出しながら、視界に入るお客さんを観察する。
若いカップル、疲れたサラリーマン、家族連れ。
彼らもきっと、私のためだけに「作られた」存在なのだろう。
実際、彼らが席を立って店を出た瞬間、彼らの存在は消えてしまうに違いない。
私が見ていない場所で、わざわざ「彼らを生かし続ける」必要なんてないのだから。
それなのに……どうして?
どうしてわざわざ嫌な客を登場させる必要があるの?
「盛り付けが少ない」とか「注文が遅い」とか、理不尽なことを言って怒鳴りつけるお客さん。
私が疲れているのを見越して、もっと優しい人だけ登場させてくれればいいのに。
そんなことを思いながら、今日も黙々と仕事をこなす。
結局、この世界は「そういう風に作られているから仕方ない」と割り切るしかないのだ。
バイトが終わって帰宅すると、家では両親が待っている。
「就職活動、ちゃんとやってるの?」
うるさい。うるさい。うるさい。
何度言われても、やる気にはなれない。
いや、私が頑張って進むべき道なんてそもそもない気がしている。
母親の問いかけに、適当に「考えてるよ」と答える。
これだって、どうせ「親役」として設定されたキャラクターなんだ。
わざわざこういう台詞を言わせなくてもいいのに。
「こんな世界、消えてしまえばいいのに!」
あるとき私が心の中で呟いた瞬間、世界は崩れた。
まるで映画のセットがバラバラに壊れていくかのように、目の前で人々は光の粒となり、建物は砂のように崩れていった。
足元が消え、闇の中に私はただ漂っているだけだった。
完全に崩壊した世界が再び元に戻るまで、三日かかった。
ただの空っぽな空間に、私一人。
それ以来、どれだけ嫌なことがあっても「世界なんて消えてしまえ」なんて二度と考えないと決めた。
私が我慢すれば、世界は崩壊しない。それが唯一のルールだ。
布団に潜り込んでLINEで友達と適当にやり取りを始める。
この時間だけは少しだけ安心できる。
眠くなってくると、私の周囲の世界は少しずつぼやけ始める。
光が薄れ、音が消え、色が褪せていく。
窓の外の景色がぼやけ、部屋の中の家具が曖昧な輪郭に溶け込む。
最後に意識が消える直前、私は思う。
「明日はもう少しいい世界を見せてほしいな」
そう願いながら、私は眠りにつく。
やがて全てが無に変わり……何もない虚空で、次に目覚めるまで私は漂っている。
—— おわり——

部屋の隅に置かれた小さな古びたバスケット。
その前で、娘が笑い声をあげていた。
「それでね、今日は学校でこんなことがあったんだ!」
母親は台所からその様子を見て微笑んだ。
娘が話しかけている相手などどこにもいない。
ただの空想遊びだとわかっていた。
それでも、彼女の楽しそうな声を邪魔する気にはなれなかった。
「お母さん!」
娘が振り向いて叫んだ。
「明日からクラブの合宿で二週間家を空けるから、このバスケットの前に毎日水を置いてあげてね。約束だよ!」
「ああ、わかったわかった」
母親は笑いながら返事をしたが、その言葉に重みはなかった。
忙しい毎日に追われる中、そんな小さな頼みごとはすぐに忘れ去られてしまった。
数日後、バスケットの中から奇妙な音が聞こえてきた。
蓋が勝手に開き、中から何かが這い出してきた。
それは形を持たない不気味な影のような存在だった。
影は台所に向かい、蛇口をひねると流れ出る水をむさぼり始めた。
しかし両親は気づかず寝室で熟睡していた。
飲むほどにその体は膨れ上がり、やがて人の背丈を超える大きさになってガラス窓を突き破り、外へと飛び出した。
二人がその音に気づいてとび起きたときはもう遅かった。
近所の人々が悲鳴を上げる中、バスケットの中にいた何かは住宅地を流れる川の水を浴びさらに巨大化……
角が生え、鋭い牙をむき出しにして咆哮を上げるその姿に、街全体が恐怖に包まれた。
怪獣が暴れ回り、建物を次々と破壊していく。
消防車や警察車両が駆けつけるが、全く歯が立たない。ついに政府は怪獣撃退部隊を出動させた。
部隊は最新鋭の兵器を駆使して怪獣に立ち向かう。
しかし、その動きは予測不能だった。
娘の想像で生まれた怪獣は、どんな攻撃にも対応し、次々と作戦を無効化していった。
「こんな恐ろしい怪獣ははじめてだ!」
部隊のリーダーが叫ぶ。
最後の手段として、部隊は戦闘用ロボットを投入。
激しい戦闘が繰り広げられる中、ついに怪獣を倒すことに成功した。
しかし、その代償として街の大半は瓦礫と化してしまった。
二週間後、娘が帰宅した。
娘は目を丸くして周囲を見渡した。
彼女を迎えたのは、かつての面影を残さない廃墟と化した街だった。
「ただいま〜」
彼女の家はガラスが割れた以外の被害はなかったが、瓦礫の後始末で両親は疲れ切っていた。
娘はケロリとして周囲のことを意に介さず、合宿の話で盛り上がった。
「ねえ、お母さん、バスケットの中のあいつに水をあげた?」
母親は気まずそうに目をそらしながら答えた。
「ああ…そのことだけどね」
娘は少し考えてから、肩をすくめた。
「あ、やってない? ゴメンね、変なこと頼んで。実はね、その話をみんなにしたらイマジナリーフレンドだって言われたんだ」
そして笑いながら
「そういうの、大人になる過程でいなくなっちゃうんだってね。友達に笑われて恥ずかしくなっちゃった……私ももう子供じゃないし、本物の友だちもできたし、もういいかなって」
母親はその言葉に驚き、同時に怒りが込み上げてきた。
「勝手に大人になってんじゃないよ! お前が置いてった童心の後始末、どれだけ大変だったと思ってんの!」
—— おわり——