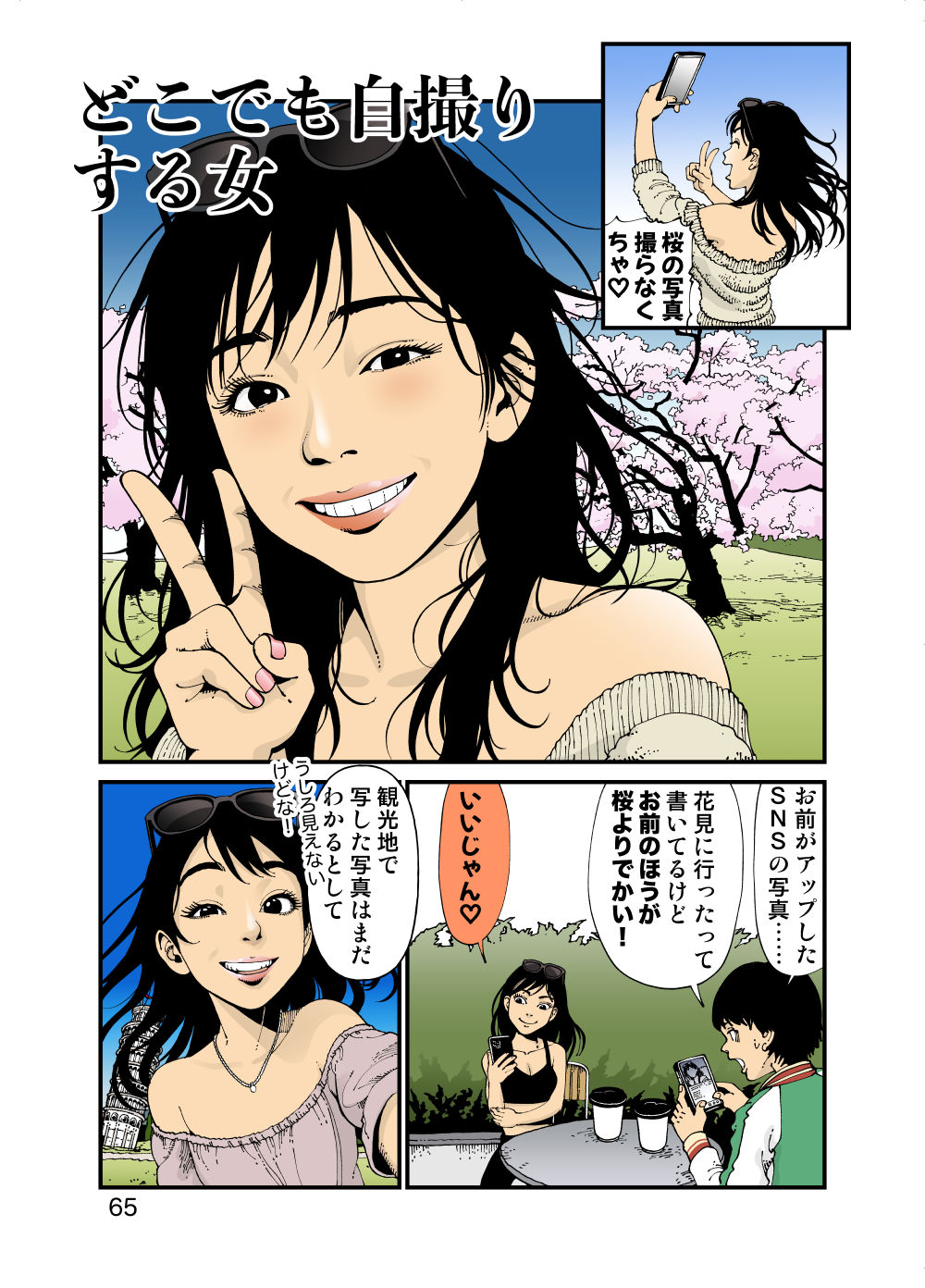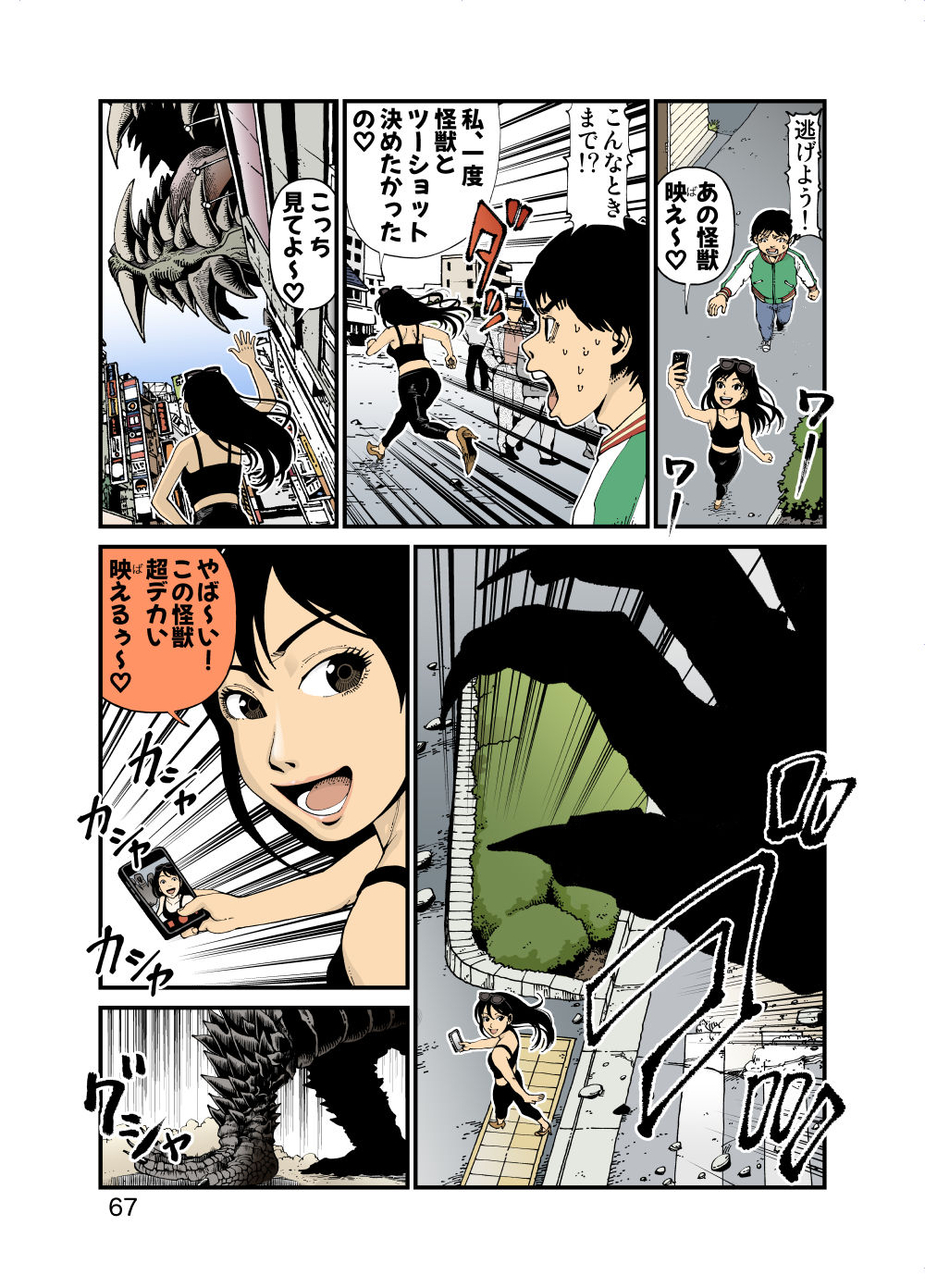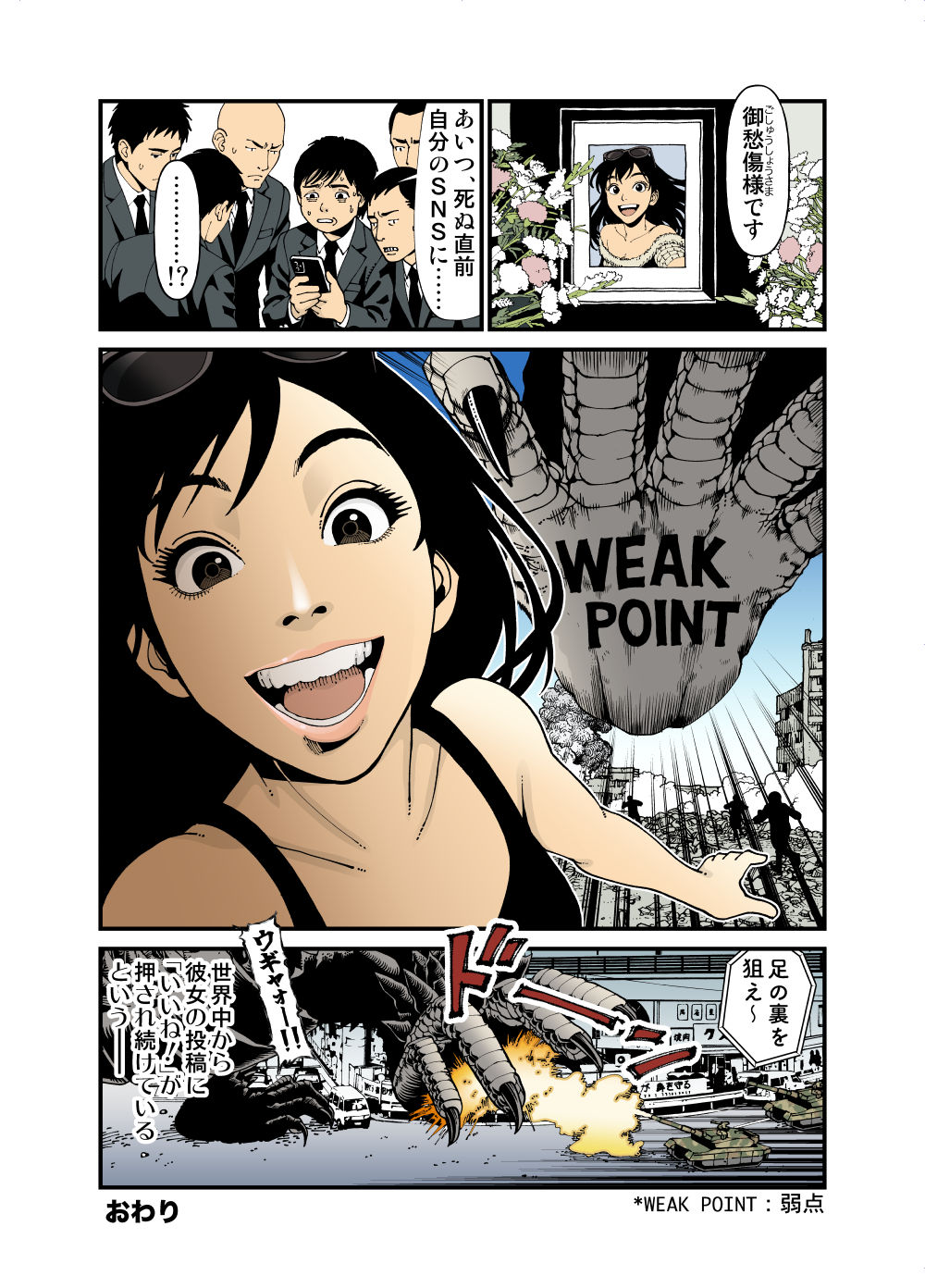月別アーカイブ: 2025年9月
【普通】 エアコンのない仕事部屋
【オネイロス】第1話 選抜①
【普通】 僕の交渉スキルを見よ!
【StoF】どこでも自撮りする女

【小説】遊園地、行きたかったね
最近、こういうサービスがある。
それは一見、未来の夢のようでいて、どこか乾いた現実の延長にも思える。
──死者の意識を保存し、仮想現実で再会する。
簡単に言えば、そういうことだ。
もっとも、その「再会」に、どれほどの意味があるのか、本当のところは誰にもわからない。
だが少なくとも、あの日の俺には、それが、救いのかたちをして見えていた。
「生きているうちにあんたと話せれば十分だよ」
と母は言うが、俺は母にいくら感謝の言葉を伝えても足りないと思っていた。
できるかぎりのことを母にしたかったのだ。
ちょうどその頃、俺は、意識保存サービスを提供する会社に勤めていた。
開発でも研究でもない、ただの営業だ。
それでも──社員特典として、格安で意識の保存を依頼できることを、俺は、奇跡のように感じた。
そのとき既に、母の老いは見て取れたからだ。
歳をとることは、記憶を遠ざけることだ。
だからこそ、消えゆく前に、せめて、残したかった。
母は協力的だった。
誰よりも淡々として、機械の前に座り、指示に従い、質問に答えた。
「こんなんで、ほんとに残るのかねえ」と言って、笑った。
……そして。
母は、その年の暮れ、ひっそりと息を引き取った。
静かだった。
病室には、冬の光が斜めに差していた。
カーテンの隙間から漏れる白さが、母の頬を淡く照らしていた。
そのほんの数時間前、母は一度だけ目を覚ました。
そのとき、まるで夢を見ていた子供のように、口元だけが動いた。
「……遊園地、行きたかったね」
何の前触れもなく、思い出したように、ぽつりと。
俺は──その言葉に、息が詰まった。
「楽しかったよ」と言いたかった。
伝えたかった。
でも、喉の奥が詰まり、声にならなかった。
音は出なかった。唇が震えただけだった。
母のまぶたが、再びゆっくりと閉じるのを、俺は何も言えぬまま、ただ見ていた。
父が早くに亡くなってから、母は再婚もせず、ただ黙々と、俺ひとりを育ててくれた。
学も、技術も、持たなかった人だった。
けれども、朝になると誰より早く家を出て、近所の工場で働き、帰ってきては台所に立った。
休みというものは、あってないようなものだった。
それでも、俺の弁当箱はいつもきちんと詰められ、制服は洗濯されていた。
生活は、つましく。
けれど、時折、ささやかな光が差すような日々だった。
日曜日、母は弁当を作ってくれた。
その弁当を持って、河原へ向かった。
木陰にレジャーシートを広げて、ふたりきりで、おにぎりを頬張った。
風が水面をなでる音と、母の「おいしい?」の声だけが、そこにはあった。
そんなある日だった。
母が職場から、遊園地のチケットをもらってきた。
俺は、胸が震えた。
生まれて初めての遊園地。
テレビの中でしか見たことがなかった、夢のような場所。
母はその日のために、ちょっとだけ手の込んだ弁当を作ってくれた。
朝早くから台所に立つ母の背中が、いつもより弾んで見えた。
そして、ゲートの前。
チケットを差し出したとき──係員が言った。
「こちら、優待券ですね。大人は二〇〇〇円、子どもは八〇〇円引きになります」
その瞬間、世界の色が、ふっと褪せた。
財布の中に、それだけのお金は入っていなかった。
それでも何度か財布を開き直し、確認し…最後に母は小さく首を横に振った。
そのまま、俺たちは遊園地の外のベンチに腰を下ろした。
「せっかくだから、お弁当はここで食べようね」
と母は、言った。
食べながら、何度も、観覧車の向こう側を見た。
音楽、風船の色、子どもたちの笑い声。
全部、塀の向こうだった。
帰りの電車の中で、母は、何も言わなかった。
顔を伏せて、車窓の外ばかり見ていた。
「……楽しかったよ」
俺がようやく言うと、母は、ふいに顔を上げ
「母さん、何も知らなくて……」
そう言って、涙を流した。
それを、俺は決して忘れなかった。
その日からだった。
俺が“貧乏”という言葉に、はっきりとした憎しみを抱いたのは。
金というものが、どれほど残酷に人間の尊厳を奪うかを、幼い俺は理解した。
だから俺は、学んだ。
とにかく学び続けた。
鉛筆を握る指が痛んでも、暗記で眠くなっても、構わなかった。
貧しさは、母のせいじゃない。
ならば俺が変えるしかないのだと。
成績は上位に並び、やがて俺は大学に進学した。
返還義務のない奨学金も得た。
もはや、それだけが目的になっていたかのように、死に物狂いだった。
そして──社会人になった。
息をつく暇もなく働き、名刺を持ち、ネクタイを締め、ようやく一人前のふりを覚えた。
なのに。
「遊園地、行きたかったね」
あのときの母の言葉が、最期の言葉だった。
それは、まるで時間の奥底から掘り起こされた石のように、重く、ひんやりとして胸に沈んだ。
母の葬式を終えてから、俺はさらに仕事にのめり込んだ。
仮想現実サービスの営業。
毎日、朝から晩まで飛び込み営業。
断られても、冷たくされても、かまわなかった。
靴底がすり減っても、声が枯れても、止まれなかった。
母のことを思えば、何も怖くなかった。
むしろ、それだけが、俺を支えていた。
上司が心配するほどだった。
同僚が引くほどだった。
それでも、止まれなかった。
──半年が過ぎた。
ふいに、ある朝、目が覚めたとき。
喉がひりつき、胸の奥が、ぽっかりと空いていた。
ようやく、その空洞に風が吹き込むように、俺は思った。
「……母に、会おう」
そのとき、初めて。
俺は、母の意識が保存されている“仮想世界”へと接続することを決めた。
母は、仮想世界の中で、今も生活している。
そう──あの頃のままの姿で。
この世界では、母は自分が亡くなったことを知らない。
俺がそう設定したのではない。
生前の母自身が、それを望んだのだ。
「死んだって知らされたら、あんたが心配してるんだって思っちゃうじゃない」
と、茶化すように、そう言った。
そのくせ、俺の姿は「子どものままにしてね」と言った。
どうやら──母は、俺の現在よりも、俺の“子ども時代”を、宝物のように思っていたらしい。
最新のヘッドセットを頭に装着し、目を閉じる。
思考がシームレスにデバイスと繋がると、空間が一度、真っ白に広がった。
落下する感覚も、遷移のざわめきもなく、ただ、ふと──
記憶の奥に沈んでいた、あの場所に、俺は立っていた。
懐かしい自宅。
風の匂い、湿った土の感触、遠くの鳥の声……
現実よりも正確に、俺の「記憶」が再構成されていた。
変色したトタン屋根の、けれどどこかあたたかく感じた借家。
今にも崩れそうな縁側、いつも少しきしむ板の間。
俺は、その場に立ちすくみ、胸の奥がぎゅうっと掴まれたような感覚に耐えた。
「ただいま──」
声は、子どもの高さで。
勝手口から、俺は中に入った。
「おかえり。今日は遅かったね」
台所の向こう、母が振り返った。
ああ──
あの笑顔。
二〇年前と寸分違わぬ、その笑顔。
俺の世界に、確かにあったその声。
母は、エプロン姿のまま、野菜を洗っていた。
現実の俺は、目を閉じながら、目を開いていた。
今この瞬間、ここは夢であり、現実であり、記憶であり、偽りであり──
そのすべてだった。
「学校帰りに木寺くんちに寄ったらね、お母さんが遊園地のチケットを二枚くれたよ」
俺は、言った。
母は、ふふっと笑った。
「ほんとう? じゃあ木寺さんにお礼言っておかないと」
母の背中は、小さく揺れながら、流しの水音と一体になっていた。
俺は、そっと、ステータスウィンドウを開いた。
仮想現実の時間を制御する、透明な盤面。
その中の時計型アイコンを、俺は指先でそっとなぞり──
時間を、“日曜日”へとスキップさせた。
日曜日。
陽はやわらかく、風はぬるく、空は雲一つなく澄んでいた。
母は朝から台所に立ち、時間をかけて、少しだけ豪華な弁当を作ってくれていた。
いつもより多めの卵焼き。
少しだけ高かったウインナー。
彩りのよい、ぎこちない花型のニンジン。
その背中が嬉しそうであることを、俺は子どもの姿をしながら、どこか遠い位置から見ていた。
母の手つき、鼻歌、ふと顔を上げるしぐさ──
どれもかつての記憶のまま、いや、もしかしたらそれ以上に、生き生きとしていた。
電車に乗ると、母は窓の外を眺めていた。
街の風景が流れ、駅を過ぎるたびに、母の頬がわずかに紅くなる。
その様子が、まるで少女のようだった。
そして、遊園地のゲートに立ったとき。
俺はゆっくりと、ポケットから「本物の招待券」を取り出した。
仮想世界で生成されたそれは、あのときの失敗を、ただ静かに、なかったことにしてくれる。
係員は笑顔でうなずき、ゲートが開いた。
俺たちは、何のつかえもなく、中へと入っていく。
母の手が、わずかに俺の袖を握っていた。
まるで、夢に触れてしまいそうで、不安になっているかのように。
中に入ると、まばゆいほどの色彩が広がっていた。
音楽が鳴り響き、ネズミのキャラクターが手を振り、風船が揺れていた。
俺は、夢中で走り出した。
母が、笑いながら後ろからついてくる。
「待って!」
叫ぶその声が、嬉しそうで、楽しそうで、切なかった。
ローラーコースターに乗って、俺たちは風の中で叫んだ。
ボートに揺られ、世界旅行のミニチュアを巡り、
射的ではお互いに張り合い、フライングカーペットでは手を握った。
笑い声が、空に弾けて、どこまでも届いていった。
昼になって、再入園スタンプを手の甲に押してもらい、ピクニックエリアへ出た。
母とベンチに腰かけて、弁当を広げる。
あのときの弁当が、本来の形で今ここにある。
あのときの弁当を、母と向かい合って食べる。
俺は、堪えきれなかった。
涙が、止まらなかった。
ひとくち、口に運ぶごとに、目の奥が熱くなる。
母はそれに気づかないふりをして、「おいしい?」と、笑った。
「おいしいよ」
その言葉が、涙の味に混じって喉を通った。
母の作る卵焼きは、どこまでも甘かった。
食べ終えたあとは、パレード。
音楽が遠くから高まり、やがてカラフルな衣装を着たキャラクターたちが、リズムに合わせて登場する。
アニメや映画でしか見たことのないキャラクターたちが、現実のような熱気と質感で目の前を通りすぎてゆく。
子どもたちが声をあげ、手を振り、大人も手拍子を打つ。
その波に、母も自然に溶け込んでいた。
あの日、塀の外から眺めていた景色。
今ここで、母がその中にいる。
「わあ……」
母が歓声を上げたとき、俺はそれを見て、目をそらした。
幸福というものが、これほど残酷に心を締めつけるのかと、思った。
笑う母の姿が、涙でぼやけていく。
何度、まばたきしても、視界がにじんで戻らなかった。
──そうだ。
この一日を、やり直すために俺はこの仮想世界に入ったのだ。
母を悲しませた記憶を、少しでも薄めるために。
あの言葉を、「楽しかったよ」という記憶に書き換えるために。
けれど、できなかった。
それが、どれほど丁寧に組み上げられた幸福の再演であっても──
俺の中に浮かび上がるのは、最期の病床の母の顔だった。
「遊園地、行きたかったね」
その声が、耳の奥でふたたび響く。
母が、自分の最期にまで引きずっていた後悔。
それを、俺がこうして勝手に「訂正」しようとしたことが、
耐えがたいほど、恥ずかしかった。
これは贖罪ではなかった。
思い出の改竄であり、死者への冒涜を、俺は、した。
「楽しかったね」
笑顔のまま、母が言った。
その瞬間──崩れた。
俺は泣いた。
しゃくりあげながら泣いた。
子どもの姿のまま、母の前で、声を抑えることもせずに。
母が顔をのぞき込む。
「どうしたの? 楽しくなかった?」
そのやさしさに、さらに涙があふれる。
俺はしゃくりあげ、心配そうに見つめる母の前で、そっとステータスウィンドウを開き──
仮想現実からログアウトした。
ヘッドセットを外した瞬間、目の奥が焼けつくように痛んだ。
まばゆい光の余韻が視界に残っているのか、それともただ涙がこびりついていたのか、しばらく何も見えなかった。
手が震えていた。
膝の上に落ちていく涙の重さが、じっとりとズボンの布地に染みていく。
それが、やけに静かだった。
部屋の静けさが突き刺さるようだった。
やがて津波のように、悲しみ、後悔、混乱、絶望、あるいは愛情と苦痛の混じり合った感情が押し寄せた。
母が亡くなったときよりも、俺は激しく泣いた。
俺は、この母との『新しい思い出』を、どう抱えて生きていくべきなのか……もう分からなかった。
—— おわり——
【普通】 夏の前半、暑苦しかった
【普通】 俺、エアコン慣れしたわ〜
【普通】 友達がいなくなった
【普通】 意識の高みからこんにちは

【小説】メダカスイッチ
大学の一角に、小さな水槽が並ぶ研究室があった。
そこではメダカの神経細胞を研究する若き学者・八ツ橋十郎(やつはしじゅうろう)が、日々メダカたちを観察していた。
彼には、特別に愛する一匹のメダカがいた。
白い体に淡い青の模様が輝くメダカ——「ふなんしぇ」。
「ふなんしぇ……君は僕の声がわかるのかい?」
八ツ橋は顕微鏡をのぞき込みながら、そっと声をかけた。
意識は特定の領域にあるのではなく、脳細胞の結びつきによって決まる。
脳の量や神経細胞の密度が意識の有無を左右するので、ネズミや爬虫類だけでなく、昆虫ですら意識を持つ可能性があるという。
メダカの大脳辺縁系に類する領域の神経活動を調べることで、彼らが本能的な行動だけでなく、ある程度の認知を持つことが示された。
メダカもまた、小さな脳の中で何かを「感じている」のだ。
彼の研究は、東京大学を含む研究グループが発表した「恋のスイッチ」と呼ばれる神経細胞の存在に基づいていた。
メダカの脳内で特定のニューロンが活性化すると、異性に対する行動が変化することを示した研究だった。
彼は、この「恋のスイッチ」の働きを応用し、ふなんしぇが自分を好きになるように仕向けようと考えた。
「もし、そのスイッチを押せば……ふなんしぇは僕を愛する?」
研究室の同僚であるウエハ坂削也(うえはざかさくや)が、それを聞いて深いため息をついた。
「八ツ橋、それは違うだろう。恋愛ってのは、操作するものじゃない!」
その言葉が、八ツ橋の胸に深く刺さった。
彼は気づいた。
愛は操作するものではなく、育てるものだ。
それから八ツ橋は、ふなんしぇにまっすぐ向き合うことを決めた。
毎日、彼女が好むエサを選び、心を込めて話しかけた。
メダカが最も好む青色の背景を用意し、彼女が快適に過ごせる環境を整えた。
変化が起こった。
八ツ橋が話しかけると、ふなんしぇはいつも何か言いたげにヒレを揺らし、じっと彼を見つめるようになった。
あるとき、ふなんしぇは急に活発に泳ぎ出し、水面まで浮かんで、必死に尾びれを振った。
「こいつ、お前に何か言いたいんじゃないのか?」
それを背後から見ていたウエハ坂が言う。
八ツ橋は顔をほころばせた。
その反応を「自分への愛情」だと確信し、彼はさらに研究を進めた。
「メダカの脳の信号を直接解析して、僕たちが会話できたら……」
メダカの脳を解析し、神経細胞の動きを調べることで「メダカ語」を解読しようとした。
八ツ橋は最新の神経科学技術を応用し、メダカの脳の活動を翻訳するプログラムを作り始めた。
ある日、八ツ橋は研究室の外へ出る際、小さな金魚鉢にふなんしぇを移すようになった。
そっと肩にのせ、大学構内を歩く——まるで恋人とデートをするかのように。
この珍妙な光景は次第にキャンパス中で噂になった。
それを笑う者もいたが、ウエハ坂は彼らに向かって毅然と言った。
「純粋な愛に満ちた二人を笑う奴のほうがおかしい!」
青空の下、八ツ橋とふなんしぇの関係はさらに深まっていった。
八ツ橋は、メダカの脳の活動パターンを人間のそれと照らし合わせ、言葉として表現できないかと試行錯誤を続けていた。
ある日、その実験の最中に、異変が起こる。
『……ヤツハシ?』
日本語に変換された人工的な女性の声が研究室に響いた。
金魚鉢の中のふなんしぇが、彼の名を呼んだのだ。
ふなんしぇはゆっくりと話し始めた。
「ヤツハシ……私は、ずっとあなたに言いたかったことがあるの」
八ツ橋は金魚鉢を眼の前に持ち上げ、期待しながら待つ。
ふなんしぇはガラスで隔てられた外界を見つめ、
『……私、ウエハザカのことが好き』
研究室には沈黙が流れた。
八ツ橋は呆然とし、後ろで立っていたウエハ坂は戸惑いながら水槽をのぞき込んだ。
「ま、待てよ……俺?」
『ええ、あなたの、友達想いの優しさに惹かれたの』
八ツ橋はそっと金魚鉢を置いた。
「……科学って、残酷過ぎる」
研究室を出ていった。
ウエハ坂は金魚鉢を前にして深いため息をつく。
(いやいや、なんで俺んとこ置いていくんだよ……)
そんな困惑をよそに、ふなんしぇは幸せそうに水の中でヒレを揺らしていた。
——おわり——

【小説】犬おじさんと過ごした夏
夏休みの始まり。
粉彦(こなひこ)は、いつものように近所の空き地を通り抜けようとして、足を止めた。
──そこに、一人のおじさんがしゃがみ込んでいた。
汗でくたびれたシャツ、泥で汚れたズボン、ぼさぼさの髪。
でも、それよりも気になったのは、彼の目だった。
悲しそうにじっと粉彦を見つめ、「くぅーん……」と小さく喉を鳴らす。
人間なのに、犬みたいな声を出している。
それだけじゃない。
彼は四つん這いで、まるで犬のように体を丸めていた。
首元には銀色のプレート。
「意識移植刑適用対象 犯罪者 No.0774」
おじさんは外見は人間のまま、意識だけが犬になっている。
新聞で読んだ記事によると、動物の意識を移植された犯罪者は、GPS、監視カメラや衛星で常時監視されているらしい。
逃亡を防ぐということよりも、誰かが過剰な危害を加えたりしないように、ということだが。
「……おじさん?」
粉彦が呼ぶと、おじさんはぴくりと肩を揺らした。
でも言葉は返ってこない。ただ、喉を鳴らすだけ。
彼は人間だったころの声を失っていた。
何かを言おうとすると、「わんっ」「くぅーん……」としか鳴けない。
「……おじさん、俺が助けてやるよ」
7月21日 晴れ
「犬おじさんはパンが好き」
今日、おじさんにパンをあげたら、四つん這いのまま食べてた。
「くぅーん」って鳴いてたけど、多分喜んでたと思う。
最初は怖かったけど、もう慣れた。
おじさんはただの「犬おじさん」だ。
* * * * *
粉彦は毎日のように空き地に通った。
お小遣いで買ったパンの切れ端や、家の残り物をこっそり持っていくと、おじさんは四つん這いのまま、それを食べた。
「おじさん、ほら、水もあるよ」
ペットボトルのキャップに少し水を入れて差し出すと、おじさんは恐る恐る顔を近づけ、ペロペロと舐めた。
まるで本物の犬みたいに。
「……おじさん、気持ちは犬なの?」
「わん」
おじさんは、わかっているのかわからないのか微妙な顔で、静かにしっぽを振るみたいに腰を揺らした。
粉彦は思わず笑った。
7月29日 曇り
「犬おじさんはかくれんぼが得意」
今日はかくれんぼをした。俺が隠れて、おじさんが探す遊び。
おじさんは鼻をくんくんさせて、すぐに俺を見つけた。
見つけたとき、「わん!」って得意そうに鳴いた。
ちょっと笑っちゃった。
* * * * *
時々、おじさんは遠くを見つめることがあった。
まるで、何かを思い出しそうに、でも、それが何だったのか分からなくて苦しんでいるように。
「おじさん、家族とかいた?」
粉彦がそう聞くと、おじさんはピクリと反応し、ぎゅっと目をつむった。
「……くぅーん……」
悲しそうな声。
その鳴き声を聞いて、粉彦は自分のことを思い出した。
粉彦の父親は、家に帰ってこなかった。
仕事が忙しいのだと母親は言うけれど、本当は別の家族がいるのだと知っていた。
たまに帰ってきたときも、母親とケンカばかりだった。
「男ならもっとしっかりしろ」「家族を支えろ」
そんな言葉ばかりで、粉彦のことなんて見ようともしなかった。
「……俺の父ちゃん、家に帰ってこないんだ」
おじさんは、じっと粉彦を見つめた。
「たまに帰ってきても、俺のことなんて全然見てくれない」
おじさんはゆっくりと、四つん這いのまま粉彦の横に座る。
そして、そっと頭を粉彦の膝に乗せた。
まるで、「分かるよ」と言いたげに。
粉彦は驚いたけれど、そっとおじさんの髪を撫でた。
父親にはできなかった触れ合いが、おじさんならできる気がした。
8月3日 晴れ
「犬おじさんは、時々悲しそうにする」
おじさんは、何かを思い出しそうになると、空をじっと見つめる。
俺のことをじっと見るときもある。
何かを思い出そうとしているかのように。
「家族いたの?」って聞いたら、黙っちゃった。
おじさんにも、俺みたいに帰ってこない父ちゃんがいたのかな。
* * * * *
「……ああ、そうか!」
粉彦は気づいた。
おじさんには子供がいるのかもしれない。
父ちゃんと同い年ぐらいだから、僕ぐらいの歳なのかな。
きっと、犬なりにそのことを思い出して悲しんでいるんだ。
粉彦とおじさんはお互い、失ったものを補いあっている関係なのかもしれない。
8月15日 雨
「犬おじさんは、俺を守ろうとした」
今日は、怖かった。
おじさんが俺の前に立って、ワンワン吠えた。
でも、俺のせいで殴られた。
ごめんなさい。
* * * * *
夏休みも終わりに近づいたころ。
粉彦が空き地でおじさんと遊んでいると、同じクラスのいじめっ子たちがやってきた。
「お前、犬と遊んでんの?」
「っていうか、これ犯罪者だろ」
「気持ち悪っ!」
そう言いながら、彼らはおじさんに石を投げた。
おじさんは身を縮める。
「やめろ!」
粉彦が叫ぶと、いじめっ子たちは粉彦を殴り始めた。
その瞬間——おじさんが飛びかかった!
四つん這いのまま、牙をむくようにして突進する。
いじめっ子たちは棒を持ち、おじさんを殴りつけた。
おじさんはいじめっ子にしがみつき棒を落とそうとしたが、後ろに回り込んだ一人がめいいっぱい振りかぶり、おじさんの顔面を棒で殴りつけた。
おじさんの右目まぶたから血が吹き出した。
粉彦は泣き叫ぶ。
いじめっ子は笑いながら逃げていった。
おじさんは、ぐったりと倒れた。
それでも、最後の力を振り絞るように、粉彦の手をそっと舐める仕草をした。
その仕草に、粉彦は思う。
「まるで、お父さんみたいだ……」
8月31日 晴れ
「犬おじさんは、いなくなってしまった」
空き地に行ったら、もうおじさんはいなかった。
昨日までいたのに。
俺のこと、覚えてるのかな。
また会いたいです。
* * * * *
おじさんの刑期が終了した。
粉彦が空き地に行くと、もうおじさんの姿はなかった。
誰かが連れて行ったのだろう。
犬だった頃の記憶が消されて、また元に戻るのだ。
そういう決まりだから、仕方がないのかもしれない。
でも……胸の奥がぽっかりとあいたようだった。
* * * * *
高校生になった粉彦は、居酒屋でバイトを始めた。
両親が離婚し、粉彦は母親と二人暮らしになったのだ。
生活費を稼ぐため、学校の帰宅時間から深夜まで働いた。
カウンター越しに酒を注ぎ、皿を運び、ひたすら客の注文をこなす。
リーダーは柚餅(ゆもち)という男だった。
年齢は四〇代。
少し疲れた顔をしているが、どこか落ち着いた雰囲気がある。
口数は少ないが、淡々と仕事をこなし、バイトの面倒も見てくれる。
粉彦は、彼を見た瞬間に分かった。
──この人は、あの夏に空き地で出会った犬おじさんだ。
しかし柚餅は粉彦を知らない。
意識移植刑を受けた者は、人間に戻るとき記憶を消される。
だから、柚餅は「犬だったころ」のことを何も覚えていないはずだった。
休憩中、先輩バイトの男たちが、柚餅の方を見ながらクスクスと笑っていた。
「なあ、柚餅さんってさ、昔『犬』だったんだろ?」
「詐欺やらかして、意識移植刑にされたんだってよ。マジウケるよな」
粉彦はドキッとした。
「どんな気分なんすか? 人間なのに犬やってたって」
「ドッグフード食わされてたんスか?」
柚餅は、何も言わなかった。
ただ、タバコに火をつけて、ゆっくりと吸う。
粉彦は、拳を握りしめた。
(ふざけるな……おじさんは、そんな人じゃない)
でも柚餅本人は、ただ静かに「仕事行くぞ」とだけ言い、厨房へ戻っていった。
その夜、粉彦はやらかした。
忙しい時間帯、客のオーダーを聞き間違えたのだ。
唐揚げを頼まれたのに、刺身を運んでしまう。
「おい、新人! 何やってんだよ!」
厨房の先輩が怒鳴る。
「オーダーミスとか勘弁してくれよ! すぐ作り直せ!」
粉彦は謝りながら、急いで動こうとする。
そのとき——
「新人なんだから、そんな怒るなよ」
柚餅が静かに言った。
「誰だって最初はミスする。お前らも入ったばかりの頃やらかしただろ?」
その声は穏やかだったが言い返せない強さがあり、先輩たちは黙り込んでしまった。
まるで——
(あの夏、俺を守ってくれた犬おじさんみたいだ……)
粉彦は、柚餅の右の目尻を見た。
ほんの小さな傷の痕が残っていた。
あのとき、俺を守ってくれたときの傷だ。
粉彦は確信した。
記憶が消えても、柚餅の心のどこかにあの夏の感情が残っている。
「お疲れ様です」
帰り間際、粉彦は柚餅に声をかけた。
「今日は……ありがとうございました」
柚餅はしばらく黙りこみ、そして。
「俺な、お前ぐらいの歳の息子がいて……今は会えないんだけど」
壁を向いて、肩を震わせた。
「お前を見ているとな、つい思い出してしまうんだ」
犬おじさんは、今でも優しかった。
粉彦は日記の続きを書くことにした。
* * * * *
4月30日 晴れ
「元犬おじさんあらため柚餅さんは、泣くのを我慢して向こうを向いて立ってました」
—— おわり——

【小説】悲報!! ワイ、入院中にゲーム貸した女の子に裏切られる
1 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:15:32.12 ID:XXXXXXXX
盲腸で入院してたとき、隣の病室の女の子(たぶん小学生)にゲーム機貸したんや
ドラクエ3やらせたらめっちゃ楽しそうに遊んでたんやけど、ワイの名前つけた遊び人(職業)がパーティーに入っとったんや
ちょっと嬉しかった
2 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:16:10.45 ID:XXXXXXXX
ほのぼのエピソードやんけ
3 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:16:45.87 ID:XXXXXXXX
かわE
4 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:17:23.21 ID:XXXXXXXX
ええ話っぽいな、続きは?
5 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:18:10.32 ID:XXXXXXXX
↓どうせ遊び人クビになる展開
6 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:18:50.97 ID:XXXXXXXX
ワイ退院 → 数週間後に病院行ったら女の子の部屋が空になってたんや……
看護師さんに聞いたら「亡くなりました」って言われた
7 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:19:30.29 ID:XXXXXXXX
えっ……
8 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:19:45.21 ID:XXXXXXXX
急に展開が重い
9 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:20:10.98 ID:XXXXXXXX
やめろや、泣く
10 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:20:45.67 ID:XXXXXXXX
まじか……
11 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:21:10.21 ID:XXXXXXXX
それでワイ、看護師さんに無理言って女の子の家を教えてもらって、ゲーム機返してもらいに行ったんや
んで電源入れてデータ見たらな……
12 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:21:55.45 ID:XXXXXXXX
(゚Д゚;)
13 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:22:30.87 ID:XXXXXXXX
データどうなってたんや
14 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:23:10.62 ID:XXXXXXXX
パーティーからワイ(遊び人)外されてたわ
イケメン先生(病院の若い医者)が戦士として入ってた
15 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:23:50.12 ID:XXXXXXXX
草ァ!!!
16 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:24:05.47 ID:XXXXXXXX
草だけど泣ける
17 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:24:30.98 ID:XXXXXXXX
結局ルイーダの酒場(待機キャラ置き場)に預けられたワイ、無事リストラされる
18 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:25:15.32 ID:XXXXXXXX
そりゃ遊び人より先生(戦士)のほうが頼りになるやろ
19 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:25:50.67 ID:XXXXXXXX
でも遊び人が最終的に賢者になるの知ってたら、外さなかったかもな……
20 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:26:10.32 ID:XXXXXXXX
>>19 そう思いたいンゴねぇ……
21 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:26:55.10 ID:XXXXXXXX
ワイ「まあ、そりゃ遊び人は役に立たないよな~ あはははは~」
ワイ「……」
ワイ「……」
ワイ「……(なみだが止まらない)」
22 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:27:40.90 ID:XXXXXXXX
やめろマジで泣く
23 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:28:20.13 ID:XXXXXXXX
名もなき少女の冒険は続いていたんやな……
24 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:29:00.52 ID:XXXXXXXX
悲しいけど、なんかええ話や
25 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:29:40.80 ID:XXXXXXXX
お前の遊び人、また旅立つ日が来るとええな
26 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:30:10.22 ID:XXXXXXXX
>>25それな、ルイーダの酒場でずっと待っとるわ
27 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:31:00.12 ID:XXXXXXXX
ワイもドラクエ3やりたくなってきたわ……
【このスレは涙で見えなくなった人たちによって沈みました】
—— おわり——