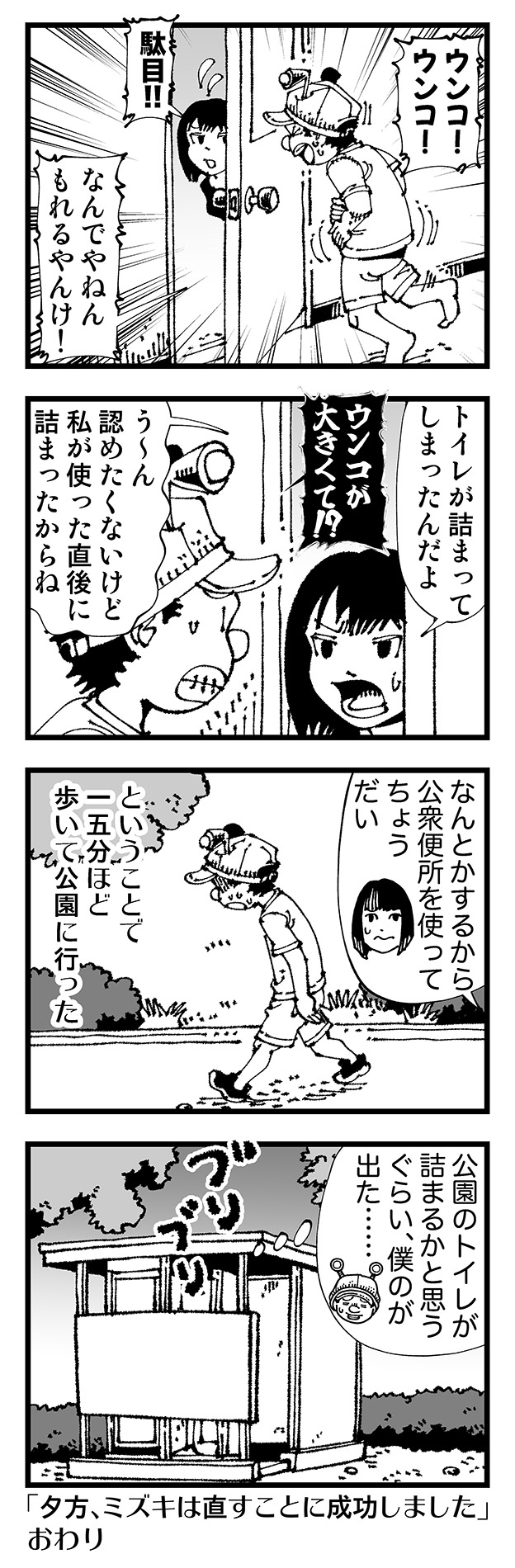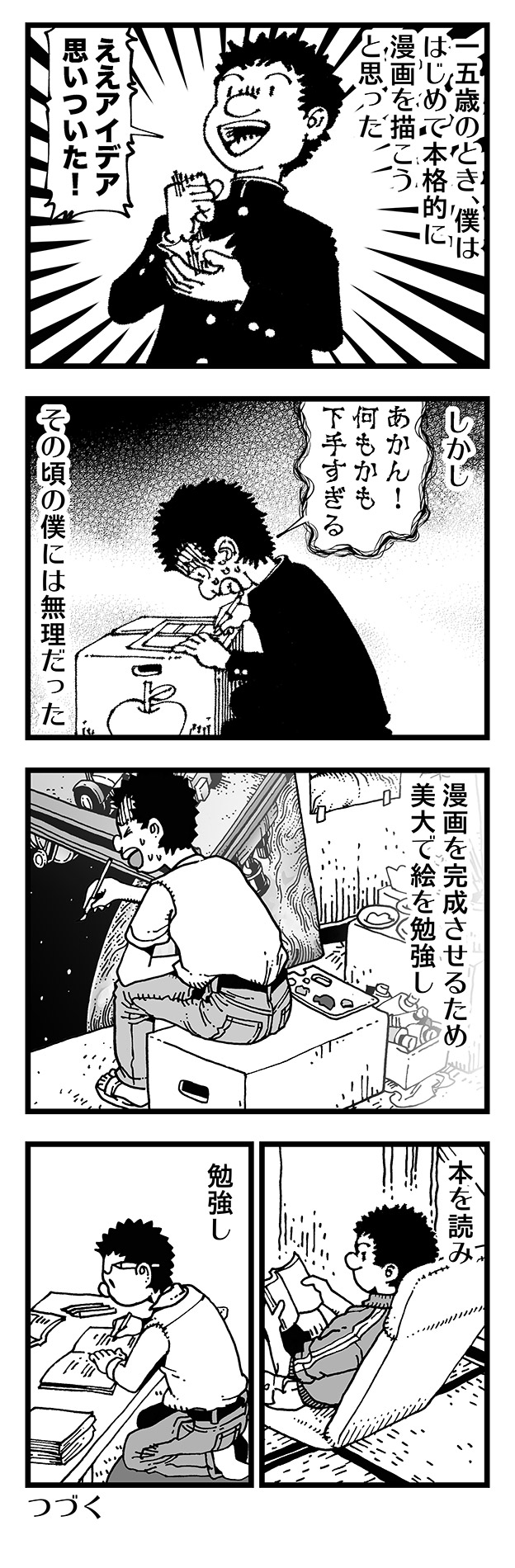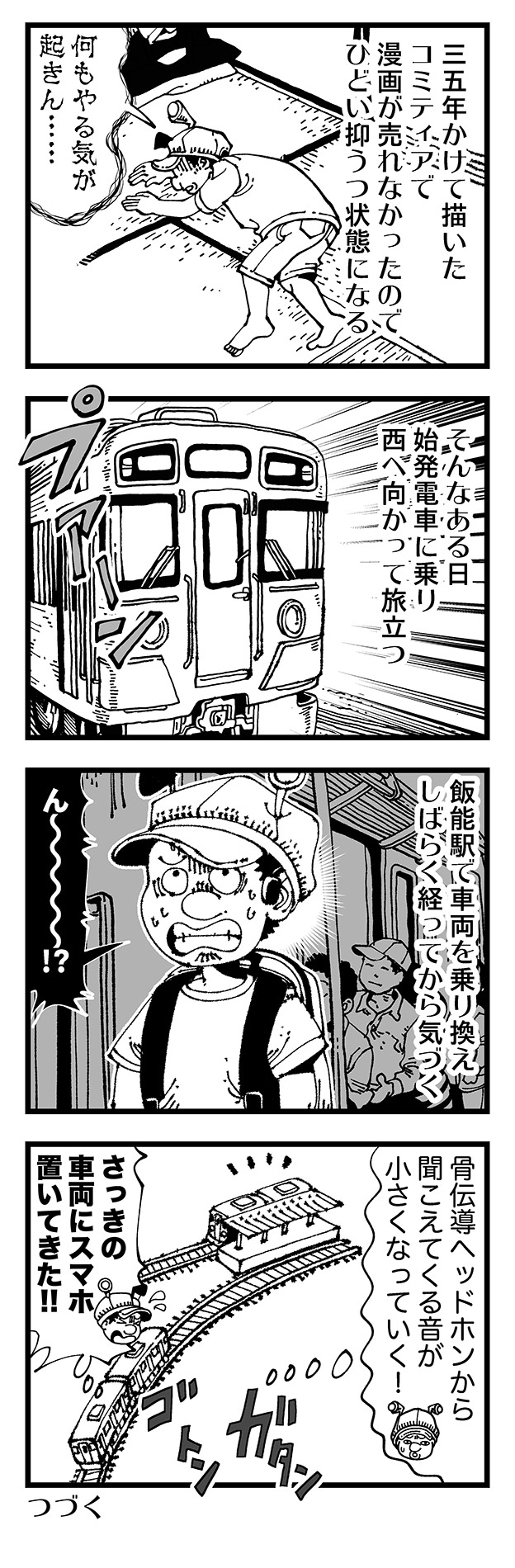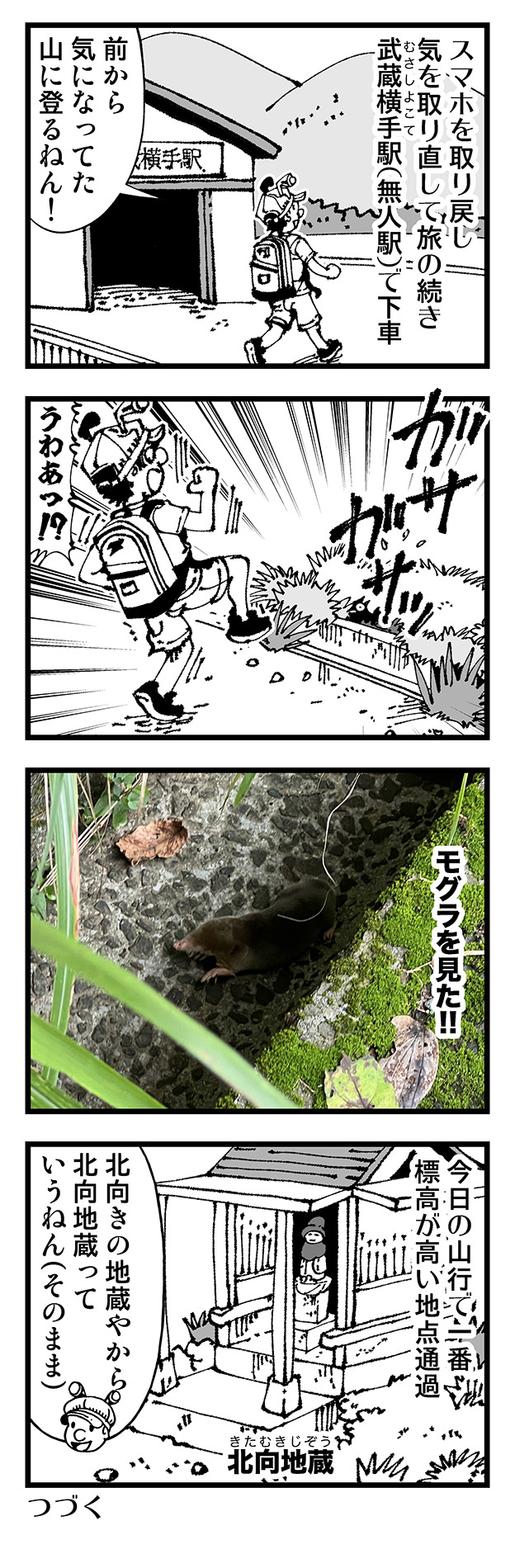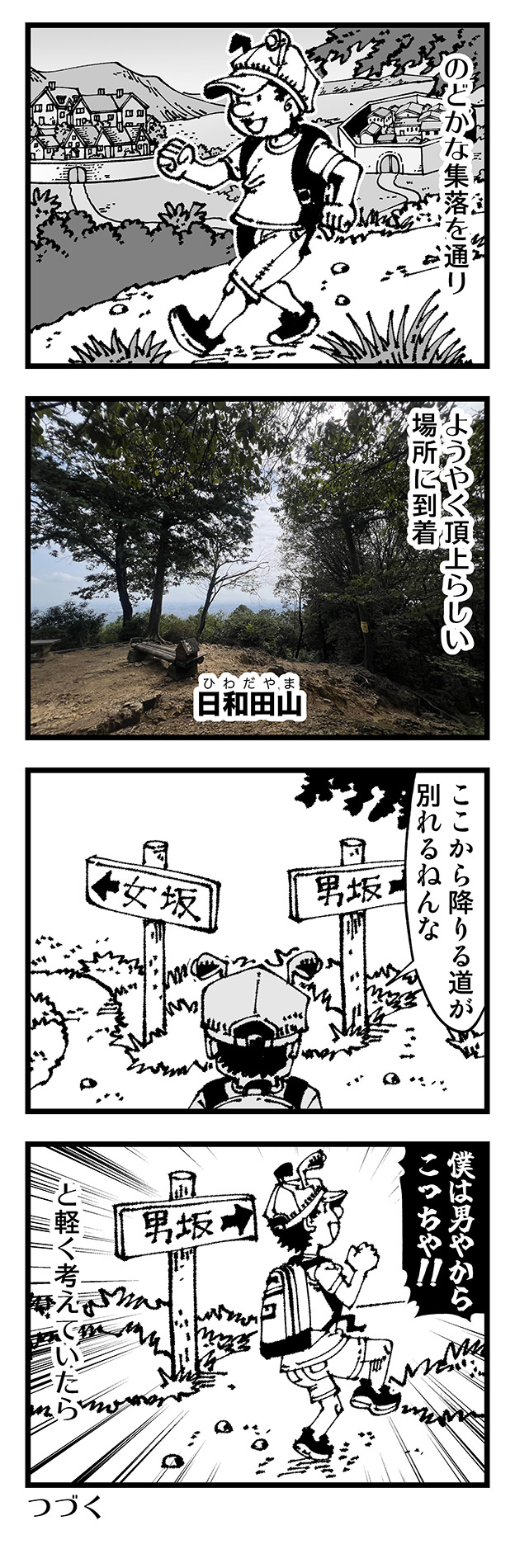餡太(あんた)がその地下倉庫に足を踏み入れたのは、十歳のある雨の日だった。
母親がいない間に、家の中を探検していた彼は、ふと、階段の下に続く扉を見つけた。
重たい扉を開けると、冷たい空気が足元から這い上がり、わずかな湿気が鼻をついた。
暗闇の中、彼はゆっくりと降りていった。ぼんやりとした照明の下に浮かび上がる光景——そこには、無数の死体が転がっていた。
すべて、子どもだった。
赤子から自分と同じぐらいの年の男の子たち。共通しているのは、顔が潰れていること。潰され、ひしゃげ、元の形を留めていない。目も鼻も口も、何もない。
餡太の背筋に氷が走った。
——これは、何だ?
目の前の光景を処理しきれず、思考が止まる。だが、一つの考えが頭の中で膨れ上がっていく。
お父さんとお母さんは、殺人者だ。
それしか考えられなかった。彼らは、子どもたちをここに閉じ込め、殺している。どうして?なぜ?
彼の心臓は激しく脈打ち、全身が震えた。
餡太は息を詰め、音を立てないように家の中を駆け回った。両親はどこにもいない。家は静まり返っている。
遠くでサイレンが聞こえる気がした
「ピンポーン♪」
家の呼び鈴が鳴った。
玄関を開けると、そこには警察官が立っていた。優しそうな顔の男だった。
「最中田(もなかだ)さんのお宅はこちらかな? ちょっとお父さんお母さんが帰ってくるまで待たせてもらえないかな」
餡太の脳内警報が一斉に鳴り響く。
——来た……!
ついに警察がうちの秘密を嗅ぎつけたんだ! この人たち、絶対に両親を逮捕しに来た!
まずい。どうしよう?どうしよう!?でも、僕はまだ捕まりたくない。まだ宿題も終わってないし、カレーの残りも食べてないし、なにより……
この家の秘密がバレたら、僕もやばいのでは!?
餡太は一瞬だけ迷ったが、すぐに決意する。
「こっちです!」
無邪気な顔で警察官の手を引き、地下倉庫へと案内した。警察官は、少し戸惑いながらも後に続く。
そして、餡太が倉庫の奥へと進んだ瞬間——
「え?」
警察官が足を踏み外す。
「わあああっ——!!」
ゴロゴロゴロッ、ドン。
音とともに、警察官は階段を転げ落ちた。
カチャン。
扉が閉まる。
——静寂。
かすかに、「助けて——」という声が聞こえた気がしたが、それもすぐに途切れた。
餡太は、じっと耳をすませた。
「……大丈夫かな?」
しばらくして、彼はホッと息を吐いた。
「よし」
数日後、また警察が訪ねてきた。
「最中田さんのお宅はこちらかな? ちょっとお父さんお母さんが帰ってくるまで——」
「こっちです!!」
またしても地下倉庫にご案内。
「え?ちょっと待っ——」
ドン!ゴロゴロゴロ!バタン!
何も聞こえない。……よし。
そして、それが何度も繰り返された。
テレビでは「最近、警察官の行方不明が相次いでいます」というニュースが流れ始めた。
餡太は震えた。
「僕、やばいことしちゃってる……?」
でも、今さらどうしようもない。こうなったら、もう警察官が来るたびに、地下倉庫に入ってもらうしかない。
「だって、秘密がバレたらおしまいだもん……」
ある晩のこと。
両親は静かに寝ている餡太を見つめていた。
「そろそろね」
「うん、餡太も成長したし……」
彼らは地下倉庫の扉を開けた。
すると——
そこには、警察官の死体がいくつも転がっていた。
両親はギョッとした。
「……なんだこれは?」
しかし、父が警察官の首元に手を伸ばし、カチッとスイッチを押すと——
——ガチャッ。
警察官がゆっくりと起き上がった。
「……再起動完了」
最初に家にやってきた警察官が言う。
「最中田さんのお父さん、お母さんですか? 困りますよ。お宅のお子さんが、近所の人からちょっとしたことで通報されちゃってね」
「そうなんですか!?」
「公園で遊んでいたボールがよその家に入ったとか、些細なことなんですけど……それにしても、なぜ私はここに?」
他の警察官も次々と再起動してムクリと起きあがる。
「……なんでこんなところにいるんだ?」
「それがわからないんです」
「強い衝撃で一時的に記憶が初期化されるようです」
「ここで転んだんですかね」
警察官たちはみんな首を傾げながら並んで階段を上がり、家から出ていく。
母が呆れたようにため息をつく。
「いったいなんなのよ……」
父親も憤慨する。
「近頃の警官の質が下がっていると聞くが、整理不良すぎるだろ!」
そして両親は、まだ眠っている餡太を地下倉庫の冷たい床に横たえて見下ろす。
「餡太も成長したし……そろそろ新しい身体に替える時ね」
母は工具を手に取る。父がゆっくりと息を吐く。
「顔を潰して電子脳を取り出そうか」
母が小さく笑う。
「成長期だからボディ交換が頻繁で、お金がかかって仕方ないわ」
——バキッ。
翌朝。
「ピンポーン♪」
新しい体の餡太が目を覚ました。
玄関のドアの向こうには、警察官が立っていた。
「最中田さんのお宅はこちらかな? ちょっとお父さんお母さんが帰ってくるまで——」
餡太はニコッと笑った。
「こっちです!」
——おわり——



の奇跡-1.jpg)