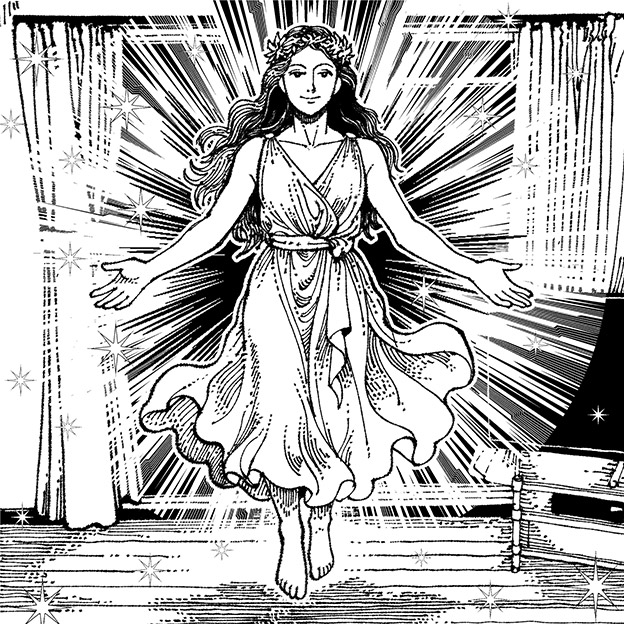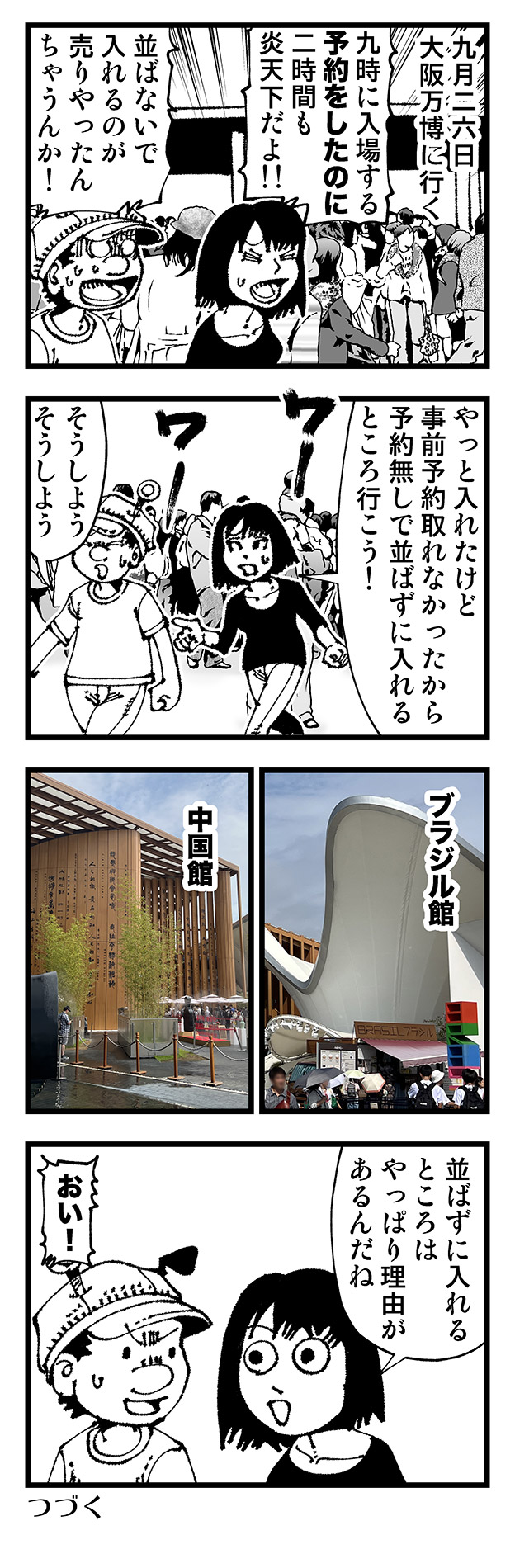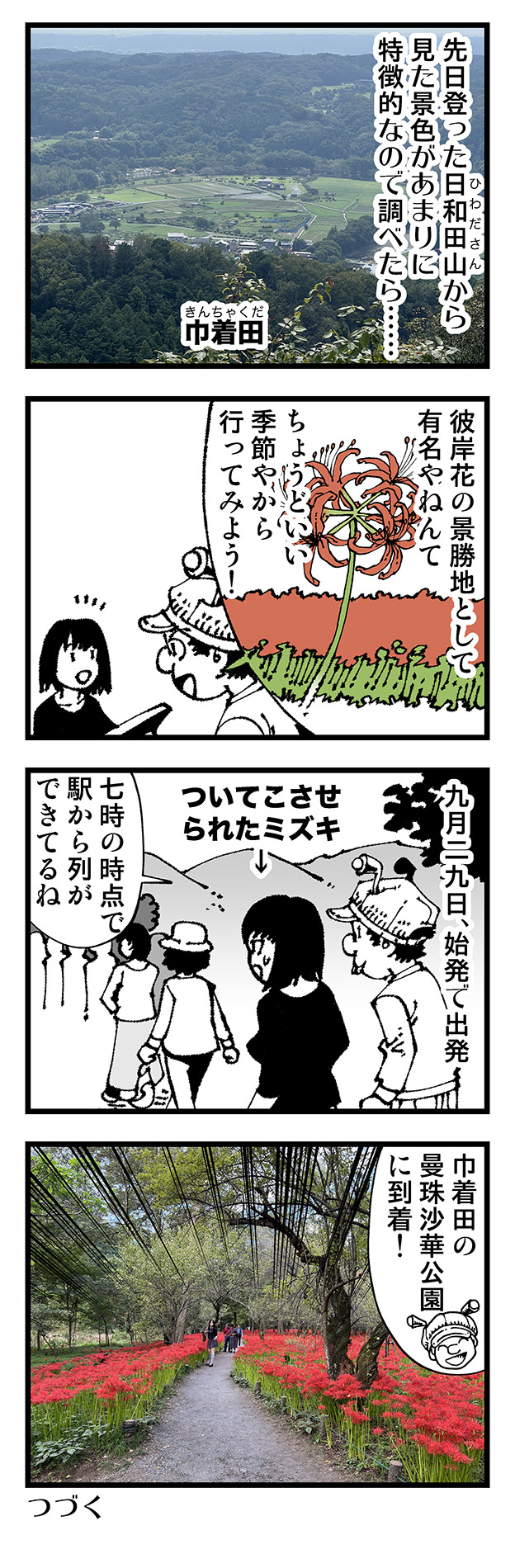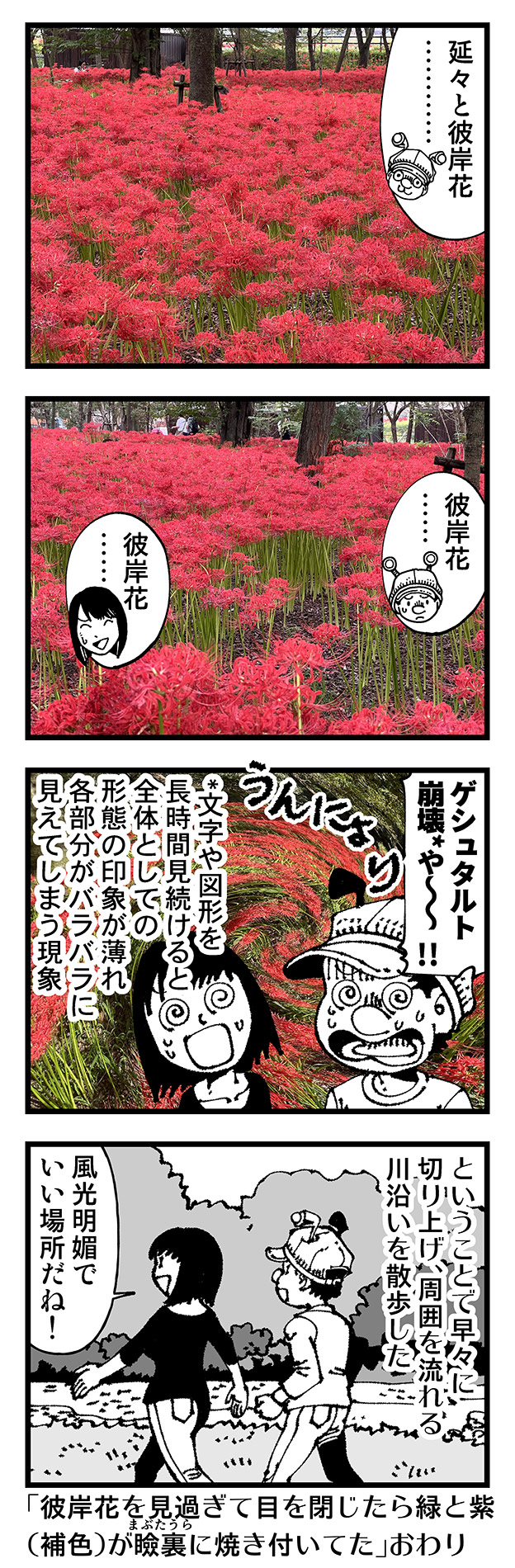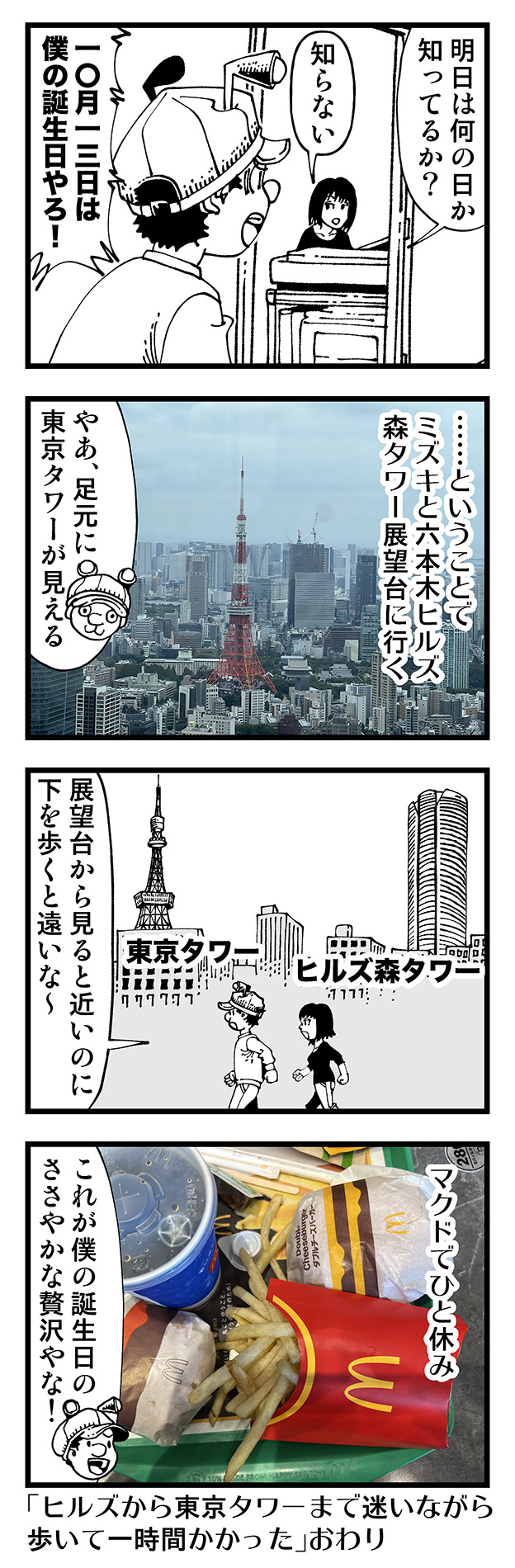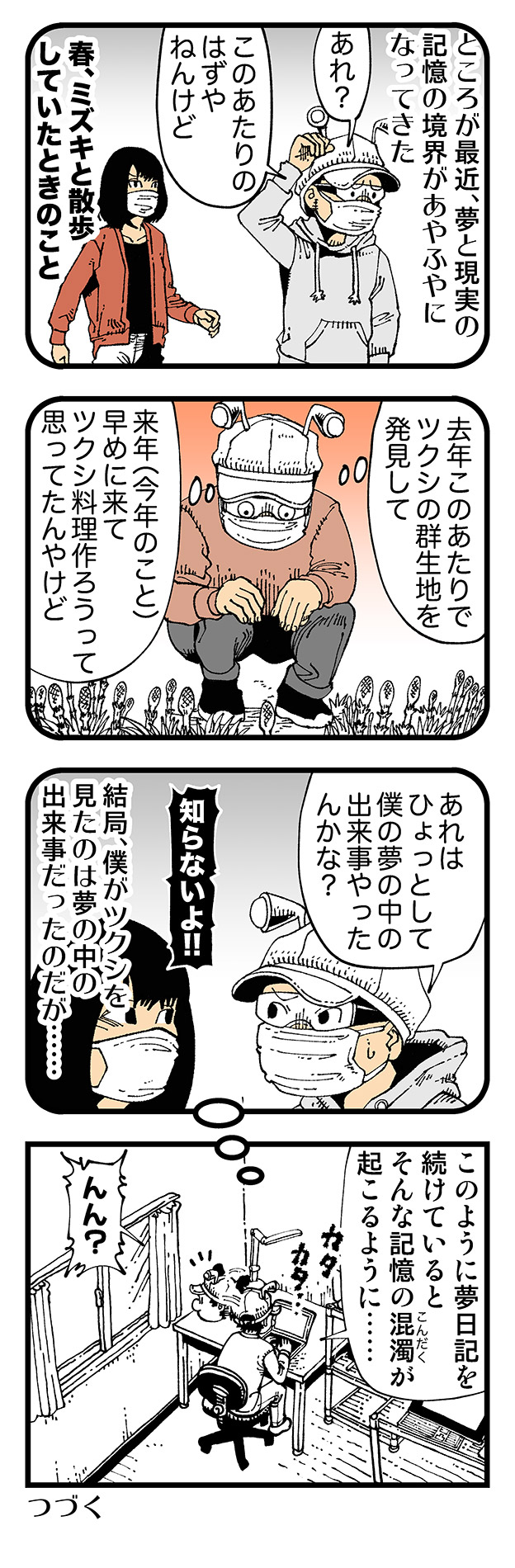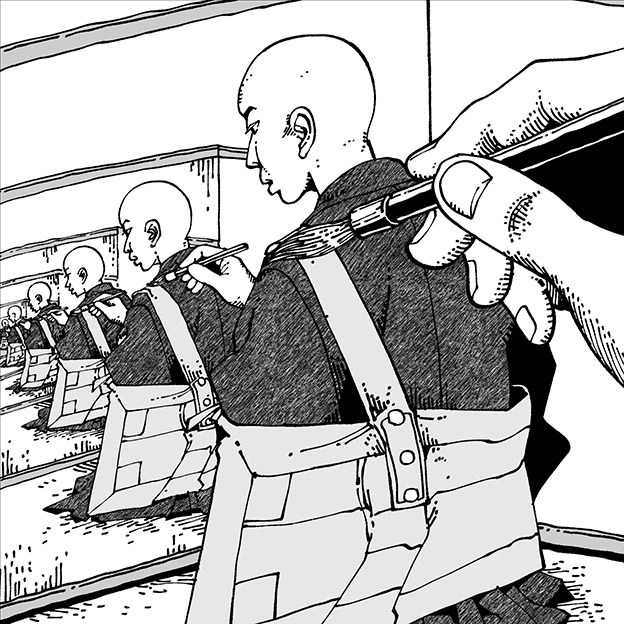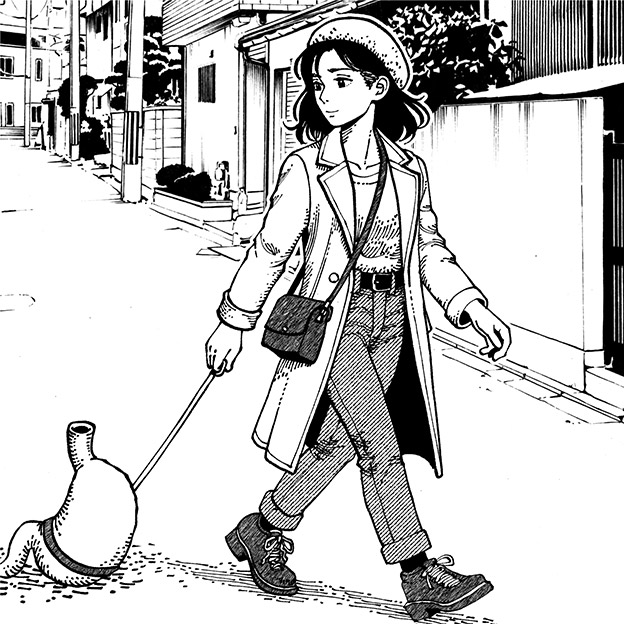メガネを掛けた青年、小太りの梨本は、自宅でリモートワークをしていた。
机の上にはぬるくなったコーヒーと、キーボードの横に置かれたスマートフォン。
ふと画面が点灯し、SNSのトレンド欄に目をやる。
「……恋人発覚」
梨本の心臓が、不意に高鳴った。
指先が震える。
まさか、と思いつつ、祈るような気持ちでその言葉をタップする。
表示されたのは一枚の写真。
明らかにプライベートな時間、街中で見知らぬ男と腕を組んで歩く、梨本の”推し”——声優・キウ井みゆの姿だった。
その瞬間、全身から力が抜け、心が沈み込む音が聞こえるようだった。
まるで世界の色が褪せていく。
キーボードの上に、涙が落ちた。
熱いものが次々と頬をつたってこぼれ落ち、視界を曇らせる。
しゃくりあげる声が、自分の口から漏れる。
「嗚呼、こんな思いをするぐらいなら……」
声がかすれ、震えながらも、彼は言葉を絞り出す。
「花や草に……生まれたかった!」
嗚咽が部屋に満ちる。
やがて、梨本は声を震わせ、絶叫した。
「世界よ滅べ!」
そのとき、梨本だけではなかった。
SNSの向こう、画面の奥に、数万、いや数十万の声があった。
各地の部屋で、同じように膝を抱え、泣きじゃくるファンたち……名古屋のアパートの一室で泣き崩れる高校生。札幌の病室で天井を見つめる余命幾ばくもない青年。
その全てが同時刻、同じ言葉を呟いた——
「世界よ滅べ」
祈りは、集まり、濃密な念となり、物質世界へ干渉した。
その瞬間。
太陽が、爆発した。
八分一七秒後。
太陽の死の閃光は、電磁波として地球に届いた。
続いて、超新星爆発で加速された高エネルギー粒子——宇宙線が、地球の大気を貫き、生命のすべてを焼き尽くした。
それからしばらくして、爆発によって吹き飛ばされた物質の衝撃波が太陽系を襲い、惑星を、月を、すべてを巻き込みながら塵と化した。
星々は沈黙し、漆黒の宇宙に細かな光の粒となって漂った。
やがて、数千万年の時を経て、その微細な粒子たちは互いに引かれ合い始めた。
ガスと塵は重力に導かれ、回転しながら円盤状へと姿を変える。
それは「分子雲」となり、やがて一点に収束する。
内部の圧力と熱によって核融合が始まり、恒星が誕生した。
新たな「原始太陽」の誕生である。
さらにそれから数億年。
惑星系が形成され、「地球」と呼ばれる青い惑星が再び誕生した。
生命が生まれ、進化が始まる。
海中に誕生した微生物は多細胞生物へと進化し、やがて陸へと這い上がった。
時間は流れ、哺乳類が繁栄し、猿から人へ。
ホモ・サピエンスが文明を築いた。
その歴史の中で、争いがあり、平和があり、科学と芸術が芽吹いた。
ある島国ではアニメーションが文化として花開き、その声を担う声優という存在が熱狂的に愛されるようになった。
再び現れた、推し文化。
声優に心を捧げる者たち——その中に、記憶を失いこの世界に新しく生まれ変わった梨本がいた。
彼は再び、キウ井みゆを推していた。
キウ井みゆはアニメ『魔女っ子♡チャップリン』に登場するモダン・ラビットの声をあてて一躍売れっ子になった。
モダン・ラビットの耳カチューシャをつけたみゆのポスターが梨本の部屋の一番目立つところに貼られている。
ライブ、ファンミーティング、舞台、公開録音、聖地巡礼——梨本は、彼女に関連するすべてを追いかけ、収入の八〇%を捧げていた。
……なのに。
再び彼は、自宅の机に向かっていた。
仕事の合間、ふと目をやったスマートフォンの画面。
「恋人発覚」
再び、あの写真。
見知らぬ男と腕を組んで歩く、推しの姿。
梨本の手が震え、涙が溢れる。
「嗚呼、こんな思いをするぐらいなら……花や草に……」
そのとき。
空気が裂けるような静寂が周囲を包みこんだ。
外は漆黒の闇に包まれ、窓の外はまるで夜のようだった。
ふと、窓の向こうに輝きが現れる。
それはひとりの女性——透き通るような光に包まれた姿。
ヒマトンを纏ったその姿は、古代ギリシアの彫像のように神々しく、まばゆく光っていた。
彼女は、すうっと部屋の中へ滑るように入ってきた。
「あなたは、また同じ過ちを繰り返そうとしているのですか?」
低く、しかし響く声。
「な、なにを……」
梨本は恐る恐る声を返す。
女神は毅然とした声で告げる。
「あなたの祈りが、かつて世界を滅ぼしたのです。四六億年前のあなたが絶望したときに発した言葉。それが宇宙を崩壊させた。私は、それを再構築するのに、四六億年もかかったのですよ」
「あなた……誰……ですか……?」
かすれた声で問う。
「私はガイア。大地の女神。すべての命は私から生まれ、私に還るのです」
彼女の身体には星々が瞬き、生命の渦が渦巻いていた。
「でも……でも、みゆちゃんが……」
梨本が再び涙をこぼすと、ガイアは慌てて口を開いた。
「泣くではない! あなたの願いは世界を滅ぼすトリガーになりかねないのです。祈りはエネルギーとなり、物理世界に干渉する集合的無意識の共鳴現象となり……」
きっと口を結ぶ。
「またこの地球を壊しかねないのですよ?」
と、梨本は、目の前のガイアをまっすぐ見つめた。
「……じゃあ、あなたが……ぼくの推しになってくれますか?」
「えっ……?」
彼女の身体に瞬く星々がわずかに揺らぎ、周囲の時間がさらにゆっくりになったように感じた。
「あなたぐらいの存在じゃないと、ぼく、もう前を向けない……」
ガイアはしばし沈黙し、自らの中で光のスピードで思いを巡らせた。
(まさか、そんな矮小な……いや、しかし、この人間の祈りは、世界を滅ぼすほどの力を持つ。これを安易に拒絶すれば……)
「だって、あなたなら僕の全部を捧げても、誰も不幸にならないでしょ? 世界を救うことになるんだから!」
歪んではいるが、梨本にとっては純粋な願い……ガイアの目に、ほんの一瞬、翳りが走った。
「……ええ、まあ……その……考えておくわ」
彼女の頬が、すこし赤くなったように見えた。
しかしガイアは、恋多き女神。
過去の恋人たち(ゼウス、ポセイドン、アポロンなどなど)さらに現在も数多の神々と浮名を流している。
この秘密が梨本に知られたら——再び「世界よ、滅べ!」と言われるかもしれない。
それは、神である彼女にとっても、途方に暮れることだった。
—— おわり——