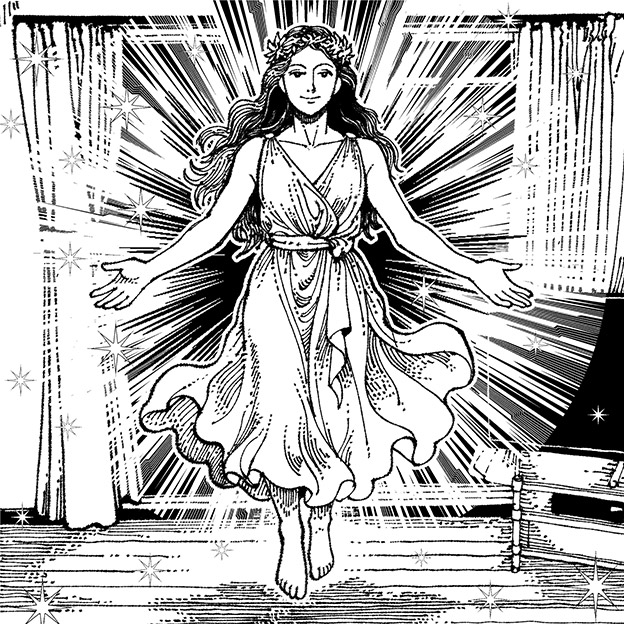関東の海辺の町に、湯の煙が立ちのぼる温泉街があった。
海鳴りは絶えず、浜風は塩を運び、軒先には古い木札が揺れ、「い〜い湯だや♪」の歌が昼も夜も響いていた。
その町に、大工の那麗(なざれ)の家があり、その家の子として伊恵寿(いえす)は生まれた。
彼は幼きころより穏やかで、人を笑わせ、人の悲しみを軽くすることを好んだ。
手のひらから湯気の立つパンを出したり、わずかな魚を一瞬で山盛りに増やしたり、さらには湖の水面を平然と歩いてみせる伊恵寿の「手品」は、どう見ても普通ではなかった。
人々は驚き、子供たちは歓声を上げた。
「伊恵寿、お前の手品すげえな!」
税務署員の息子真鯛之助(またいのすけ)は叫び、
「俺はこいつに弟子入りする!」
瓶手郎(ぺてろ)は膝を叩く。
枕田(まくらだ)の麻莉亜(まりあ)は微笑み、
「本当にすごいよね! 神さまのような力を持っているのかしら」
と感嘆の声を漏らすと、子門(しもん)も
「そうだよ! 救世主とかさ!」
と茶化す。
伊恵寿は笑って首を振った。
「救世主なんて大げさ! ただの大工の息子さ。湯気が立つのも、魚が群れるのも、自然の働きなんだよ」
彼の声は柔らかく、海辺に響く波音のようであった。
だが、椅子借桶(いすかりおけ)の雄太(ゆだ)だけは、その様子を遠巻きに見つめるだけだった。
「あれは、ただの手品ではないぞ……」
彼だけは心の奥底にわだかまりを抱えていた。
* * *
夏の終わりに、記録的な台風が近づいた。
海は黒く泡立ち、港の防波堤を越えて波が打ちつけた。
風は瓦を飛ばし、看板を折り、「い〜い湯だや♪」の音楽も、ちぎれたテープのように途切れ途切れになった。
港に集まった若者たちは、荒れ狂う波を見ながら興奮していた。
「嵐の海で釣りしたら、きっと大物が釣れるぞ!」
誰かが叫び、笑いが起きた。
雄太は止めようとした。
「やめろ! これは洒落にならない。死ぬぞ!」
だが、誰も聞かなかった。
そのとき、伊恵寿がすっと前に出た。
彼は濡れた髪をかき上げ、空を仰いで言った。
「静まれ」
その声は風よりも強く、嵐の音を押し返した。
海はたちまち凪ぎ、波のうねりは消え、厚い雲が裂けて光が降り注いだ。
浜辺に集まった者たちは息をのんだ。
太陽の光は金の矢のように海面を射し、白い泡が光を受けてきらめいた。
人々は歓声を上げたが、それは恐れではなく、笑いに似ていた。
「また手品だ!」
「やるな、伊恵寿!」
誰もそれを奇跡とは呼ばなかった。
ただの見世物。湯けむりと同じ、一瞬で消える幻想。
しかし、雄太だけは、その光景を見つめながら凍りついていた。
「これは……手品なんかじゃない」
伊恵寿は雄太の方を振り向いた。
潮風に髪をなびかせ、まるで何もなかったかのように笑い、手を振った。
雄太の胸に、言葉にならない熱が宿った。
羨望、恐れ、そして——疑い。
「なぜだ?」
「奇跡が奇跡であることを、なぜみんな気づかない?」
風が再び吹き始め、海はいつもの姿に戻った。
嵐は去ったが、雄太の心には、嵐が残ったままだった。
「伊恵寿はその沈黙の裏に、何を抱えている?」と。
* * *
日が経つごとに、伊恵寿の名は町のあちこちで語られた。
「魚を増やす若者」「湯けむりの魔法師」「海を鎮めた男」。
その呼び名は誇張され、笑い話として広まった。
しかし、彼を慕う者たちが増えていったのも事実だ。
彼らはいつしか「十二使徒」と呼ばれるようになった。
彼らの住む温泉街は数年前、平成の大合併によって驢馬(ろうま)市に組み込まれていた。
効率化という名のもとに、公民館も図書館も学校も次々と統廃合され、人が集まる場所が消えていった。
湯の町は地図の上では一地区にすぎなくなり、観光客は減り、灯りは減り、声も減った。
「十二使徒」を中心に、温泉街の若者たちは、長いあいだ湯けむりの下で眠っていた町に、もう一度新しい息を吹き込もうとしていた。
「この町を変えよう」
彼らは浜辺に集まり、古い演歌調の「い〜い湯だや♪」をジャズに編み直し、波音をリズムに即興の演奏を始めた。
笑い声が湯けむりに混じり、久しぶりに町に音が戻った。
夏には手づくりの音楽祭を開き、地元の食堂や旅館を回って協力を求めた。
「観光客に頼らず、自分たちでこの町を立て直したいんです」
若者たちの声は真剣だった。
「い〜い湯だや♪」を歌う伊恵寿の歌声が響く。
その声を聞くと病気が癒やされる、という不思議な噂が立った。
歌声は静かに熱を帯び、湯けむりの向こうに見える海が、彼らの熱を映すようにゆらゆらと銀の光を返した。
彼らは最終的に驢馬(ろうま)市からの独立を目指していた。
だが、組合の古老たちは怒った。
古びた旅館の座敷で、組合の重鎮たちは湯呑を置き、伊恵寿を呼びつけた。
「お前のやっていることは何だ」
「手品や音楽で若者を煽ってどうする」
「湯守の掟を忘れたのか」
伊恵寿は静かに座り、頭を下げた。
「みんなに笑ってほしいだけなんです。湯の町が、また賑やかになればそれで」
だが、古老たちは聞かなかった。
平成の大合併から長く経ち、彼らはすでに驢馬の富裕層と癒着関係にあった。
もう引き返せない。
伊恵寿は責め立てられた。
「お前は湯の秩序を乱す者。若者を惑わせる者だ」
古老たちは机を叩き、怒声を浴びせた。
後ろで瓶手郎がつぶやいた。
「これじゃまるでムチ打ち刑だよ……」
鶏が三度鳴く時刻。
会は散り、人々は湯けむりの夜道を黙って帰った。
伊恵寿と雄太だけが残り、海へと続く坂道を歩いていた。
「みんな、お前がこの町を変えてくれると信じてる」
「そんな大層なもんじゃないよ。僕はただ、大工の息子だから」
「でもさ……お前には、何かある」
雄太の目には、かすかな怒りと祈りが混ざっていた。
「お前のパンは湯気を立て、お前の魚は増える。お前の足は水の上を歩く。それを奇跡と呼ばずに何と呼ぶ?」
伊恵寿は肩をすくめた。
「奇跡を見たいなら、湯気を見上げたらいい。誰もが見たいものだけを信じるのさ」
しかし、雄太は追及をやめなかった。
「そういうことじゃない! お前、本当は手品じゃなく——」
十字路に差しかかったそのとき、背後から車のクラクションが鳴り響いた。
猛スピードで突っ込んできた車は、雄太の目の前で伊恵寿をはね飛ばした。
伊恵寿の体は宙を舞い、地面に叩きつけられた。
即死だった。
* * *
伊恵寿の死は、湯の町に重い影を落とした。
港の風は止み、潮騒は喪のように低く響いた。
「雄太が……裏切ったんじゃないか?」
誰かがつぶやいた。
その声は湯けむりのように町中に広がった。
「だって、あの夜、二人きりだったんだろ」
「伊恵寿は、雄太を信じてたのに……」
雄太は否定した。
「俺は何もしてない! ただ隣にいただけだ!」
だが、瓶手郎も真鯛之助も目をそらした。
麻莉亜は泣きもせず、子門は煙草をくわえたまま言った。
「人は奇跡より噂を信じるもんだよ」
それから三日が過ぎた。
台風は遠くに去り、海は再び静まりかえった。
だが、人々の心には、まだ嵐が吹き荒れていた。
三日目の朝、町の火葬場には伊恵寿の棺が運ばれた。
組合の長老も、若者たちも、みな白い喪服に身を包み、黙って列をなした。
* * *
火葬炉の扉が閉まると、鈍い音を立てて炎が灯った。
湯気と煙がゆっくりと上昇し、天井の換気口から外へと流れた。
そのとき、誰もが忘れられない声を聞いた。
「うう〜! あつい〜! 助けてくれ〜!」
職員たちは凍りついた。
炉の温度は千度を超えている。
中に、生きた声があるはずがない。
瓶手郎が叫んだ。
「伊恵寿……なのか?」
「嘘だろ……復活したのか?」
麻莉亜は口を押さえ、雄太は震える声でつぶやいた。
「……やっぱり、奇跡なんだ」
声は続いた。
「あつい〜! もうダメだ〜!」
炎が唸り、鉄が鳴り、やがて声は途絶えた。
炉が冷え、扉が開かれたとき、そこに残っていたのは白い骨だった。
それは、奇妙なことに十字架に貼り付けられたかのようなポーズをしていた。
沈黙が落ちた。
瓶手郎は言った。
「これ……最後の大手品じゃないか?」
自分を納得させるように、真鯛之助はがくがくと首を振った。
「伊恵寿らしいよな。最後まで人を驚かせる」
麻莉亜は微笑み、子門は肩をすくめた。
「自分の死まで笑いに変える。ホント、すごい奴だ」
火葬場の外では、セミが鳴いていた。
その声はまるで、空に昇る湯気のように淡く消えていった。
* * *
帰り途、「十二使徒」全員で肩を並べて海沿いの道を歩いた。
月が波間を照らし、白い光が漂っていた。
「もし、あいつが本当に救世主だったなら……俺たちは、ひどいことをしたんじゃないか?」
雄太の問いかけに誰も答えなかった。
温泉の排気塔から、ふわりと湯気が上がり、月光の中に溶けていった。
雄太は顔を上げた。
夜空には雲の裂け目があり、その向こうに星が瞬いていた。
「信じないってのは……あいつにとって、一番つらかったんじゃないか?」
黙して語るものは誰もなかった。
翌朝、湯の町は何事もなかったように目を覚ました。
「い〜い湯だや♪」の音楽がまた流れ、湯けむりは穏やかに空へと昇った。
人々は言った。
「昨日は嵐もなかったし、火葬も無事終わった」
「やっぱり、伊恵寿はいい奴だったな」
「最後まで笑わせてくれた」
そうして、誰も奇跡を語らなかった。
ただ「あいつはたいした手品師だった」
と笑いながら、温泉まんじゅうを頬張った。
——おわり——


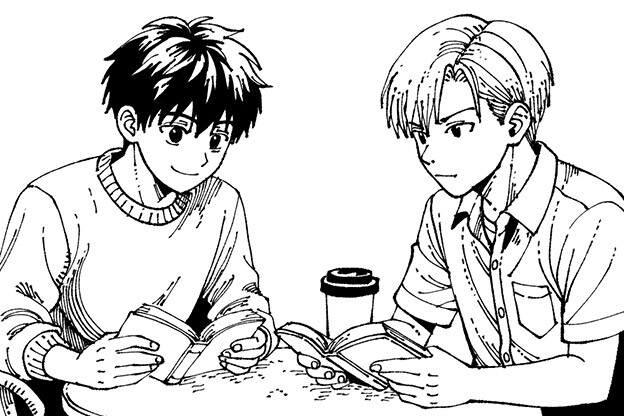









の奇跡-1.jpg)