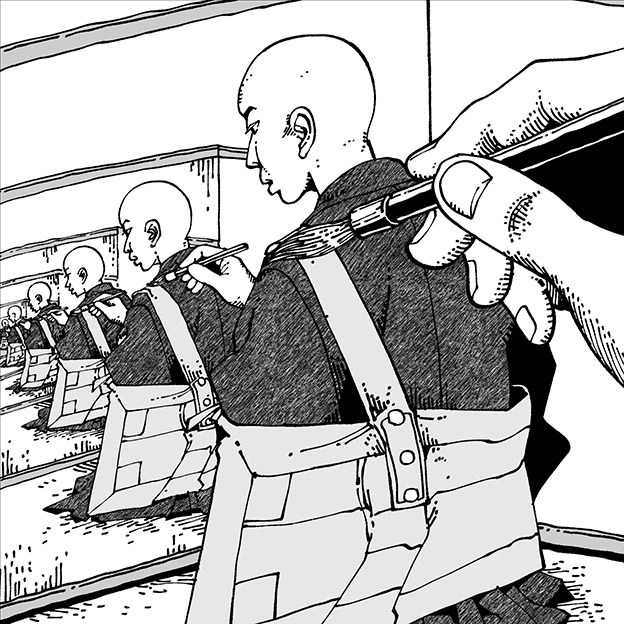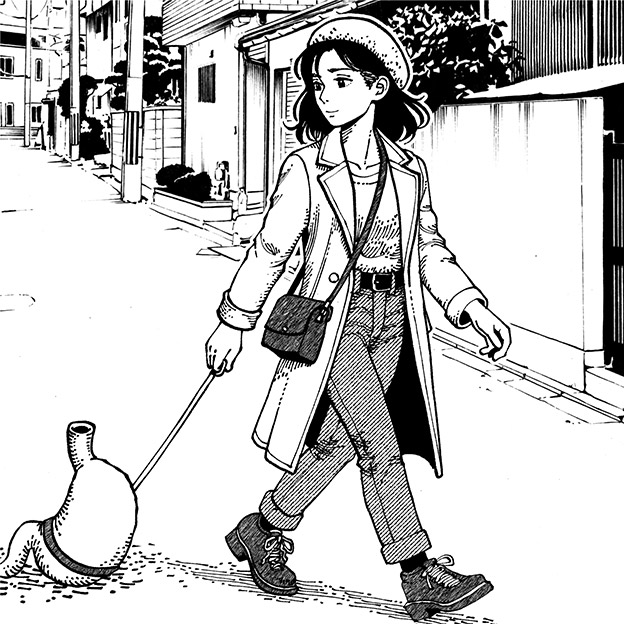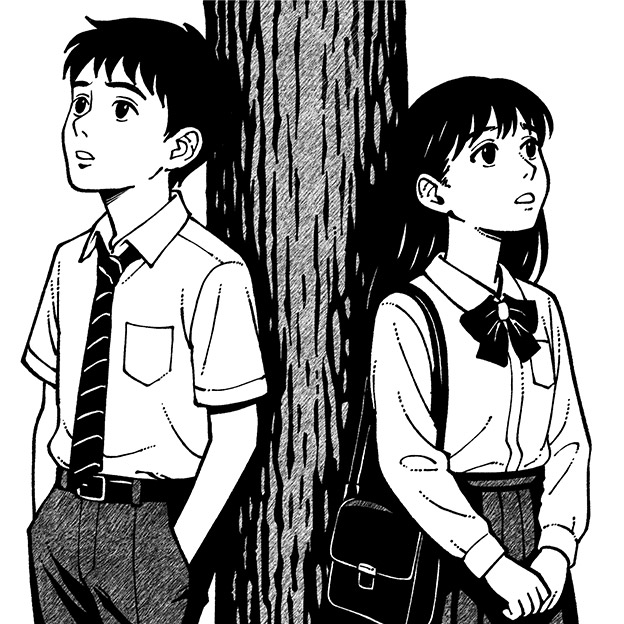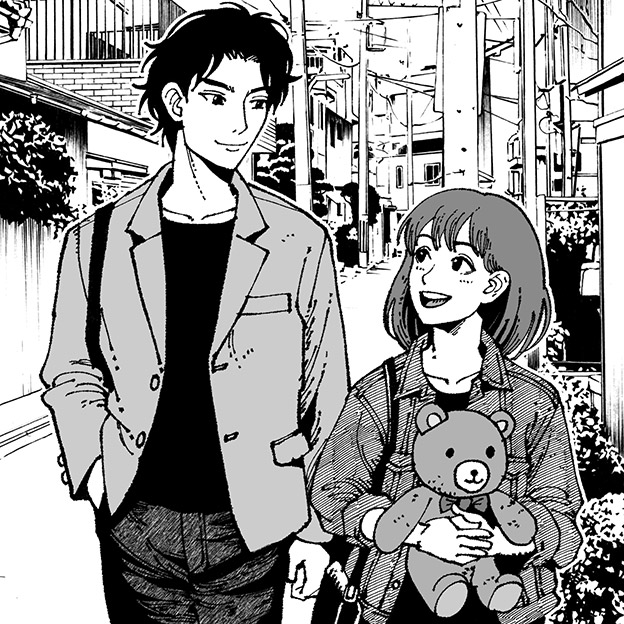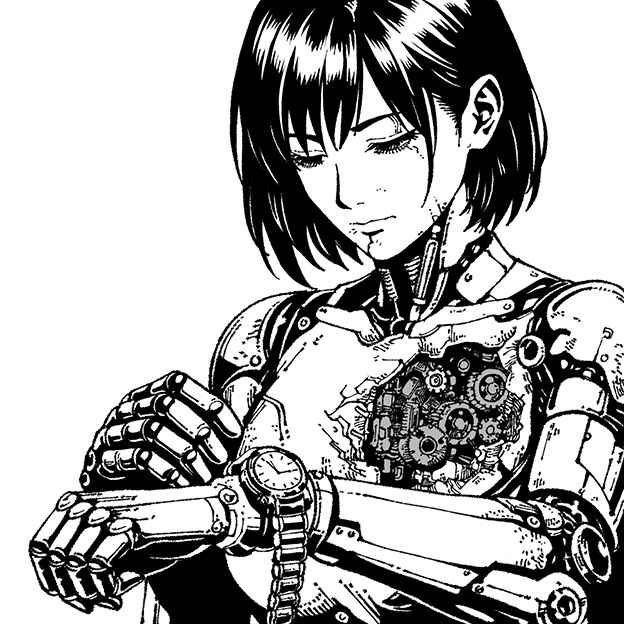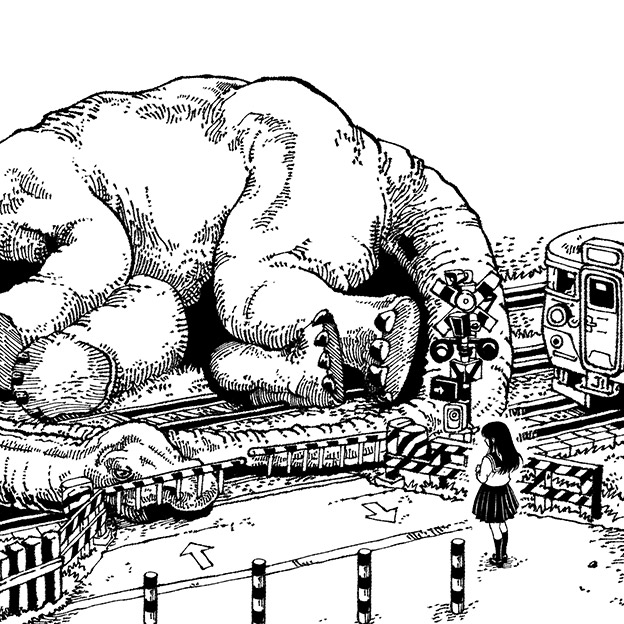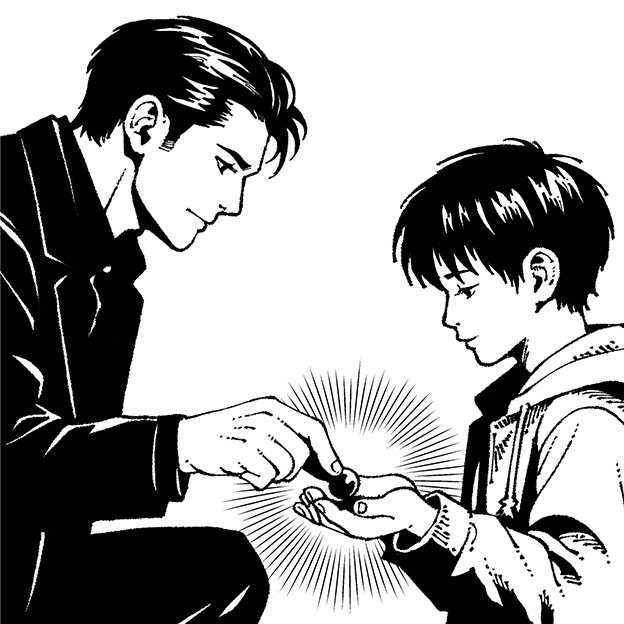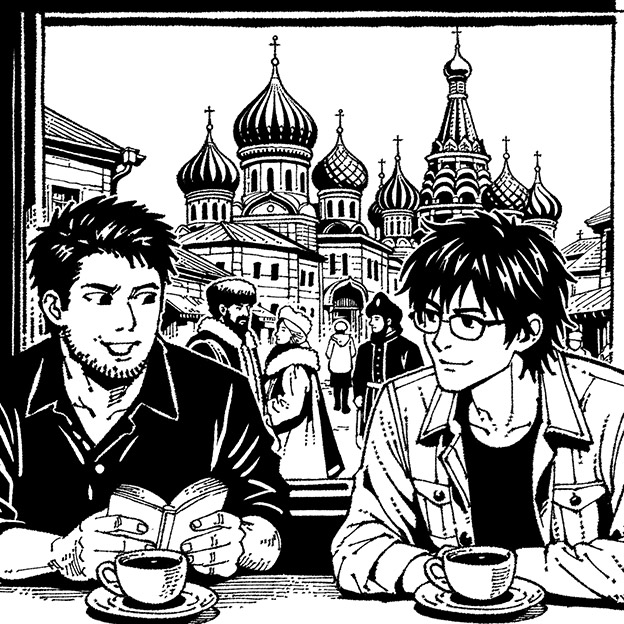「私、東京の大学に行くんだ」
葛葉(くずは)がそう告げたとき、僕は驚いた。
地元でずっと一緒にいるものだと思っていた。
二人の未来も、この町で続くものだと信じて疑わなかった。
だけど僕も東京に行って一緒に暮らせばいいか、とすぐ考え直した。
——二人はずっと一緒だから。
僕がそう言うと彼女は嬉しそうだった。
卒業式の日。
「私、こんなに泣くか〜っていうぐらい泣いちゃった。クラスのみんなとバラバラになったけど、君とはずっと一緒だよ」
彼女はそう言った。
僕は強く抱きしめた。
なのに引っ越しの前日、葛葉は泣きながら言った。
「君とは一緒に行けない」
シェアハウスで知らない人たちとルームシェアしながら暮らすことになるから、と。
ショックだった。
「でも、休みになったらきっと帰ってくるから、そのとき会おうね」
——ぜったいだよ!
僕らは指切りげんまんした。
そして彼女は僕を郷里に残し、去っていった。
葛葉のいない生活は味気なかった。
時々、彼女のお母さんと会って話を聞いた。
葛葉は元気に過ごしているようだった。
それが少しの安心になった。
僕はずっと彼女を待ち続けた。
陽の当たる場所で、僕は窓の外を眺める。
春、柔らかい陽光がカーテンを透かして差し込んだ。
窓の外には桜が咲き、風が花びらを巻き上げた。
陽が落ちると、葛葉と過ごした日々を思い出しながら、僕は小さくうなずいた。
——また帰ってくるよね、と。
彼女のお母さんも、僕を励ますように言ってくれた。
「葛葉、じき帰ってくるわよ」
夏、空は青く、蝉が力強く鳴いた。
窓を開けると、遠くから祭りの太鼓の音が聞こえた。
葛葉と一緒に見た夏の夜の花火を思い出す。
汗がにじむような気がした。
夏も半ばを過ぎた頃、とうとう葛葉は帰ってきた!
すごいテンションで話し続けた。
芸術学を研究していること、演劇部に入ったこと、ルームシェアしている友達とも仲良くなったこと。
「充実してそうでしょ?」
彼女はそう言って笑った。
嬉しそうな彼女を見て、僕も嬉しかった。
でも、気になることを彼女は口にした。
「演劇部の先輩が気になってて……」
——そんなこと言わないで。
僕は気になって仕方がなかった。
「大丈夫だって、嫉妬してるの?」
——そりゃそうだよ!
「大丈夫、またすぐ帰ってくるからね」
けれど、彼女はなかなか帰ってこなかった。
秋、風が冷たくなり、色づいた葉が舞い落ちた。
木々の間を歩く子供たちの足音が微かに響く。
時折、ドアが開く音がすると、彼女が来たのではと胸が高鳴るけど、いつも違った。
秋の終わり頃、彼女のお母さんと会ったとき、ぼそりと呟いた。
「葛葉、今年はもう戻ってこないみたい……」
僕は何も言えなかった。
ただ窓の外の山々を見つめるだけだった。
冬が深まり、町は静けさに包まれた。
雪が降る夜、部屋の奥から聞こえてくるストーブの音が妙に遠く感じる。
葛葉は、冬休み帰郷しなかった。
桜が舞い散る季節、ようやく葛葉は帰ってきた。
彼女の髪は真っ赤に染められていた。
「びっくりした?」
僕は言葉を失った。
彼女はせっかく僕のところに来ても、少ししか相手してくれなかった。
悲しい。
次の夏、彼女はもう帰ってこなかった。
お母さんにもあまり連絡が来なくなったらしい。
東京が楽しいのかな。
悲しい。
悲しい。
思いは募るばかり。
僕は音の出ないため息をつく。
このままでは、彼女の世界から僕は完全に消えてしまう。
僕らは終わる。
焦りと裏腹に、窓の外から見える山々は色づき紅葉に覆われていく。
彼女が座っていたあの窓辺に寄り添うように、僕は座って外を眺めた。
東京ってどういうところなのだろう。
彼女が歩く街の景色は、どんなふうに見えるのだろう。
悲しい。
悲しい。
悲しい。
…………
僕は意を決して葛葉に会いに行くことにした。
胸の奥の綿が軋む。もう躊躇していられない。
——今行かなければ、もう会えないかもしれない。
引っ越しの日、僕もその場にいたから、ルームシェア先の場所はなんとなく覚えていた。
場所はわかっている。
でも、本当に会ってくれるだろうか?
上りの鈍行列車に飛び乗ったつもりだったが、気がつくと誰かの荷物にまぎれ、見知らぬ列車の床の上で揺られていた。
窓の外を流れる景色は目に入らなかった。
頭の中は彼女のことでいっぱいだった。
「葛葉……」
僕は何度も彼女の名前を呟いた。
何度も違う電車に揺られながら、ようやく東京の奥へ奥へと運ばれていった。
東京の駅は迷路のようだった。
すべてが大きすぎる。早すぎる。
都会の人間たちの歩くスピードに、僕は飲み込まれそうになる。
汗がにじむような気がした。
胸の綿がきゅっと詰まる。
息が苦しい気がした。
でも、それでも歩みを止めるわけにはいかない。
落とされそうになりながら、それでもどうにか……彼女のシェアハウスの近くにたどり着いた。
深く息を吸い込む自分を想像した。
そして——
たった一歩の距離が、これほど遠く感じたことはなかった。
そのときだった。
見知らぬ男と歩いているのが見えた。
声をかけようとしたが、驚きで体が動かなかった。
と、葛葉が振り返り、彼女の視界に僕が入った瞬間……
僕は力が入らず倒れた。
* * *
「あれ? あれ〜!?」
葛葉は、目の前で倒れた小さなものを見て驚いた。
それは、彼女が幼いころから一緒にいた、クマのぬいぐるみだった。
ぬいぐるみは、葛葉に恋人と呼ばれ続けたからずっとそのつもりでいた。
しかし、今、彼女の隣には別の誰かがいる。
「何でこんなところに〜!? クマさん、どうしたのかな」
彼女は実家に電話をかけ、部屋にクマさんがあるか母親に尋ねる。
電話を切った後も首を傾げている。
葛葉は懐かしむような仕草でクマさんをひょいと拾い上げた。
その腕の中に抱えられた一瞬、クマさんの胸の綿の奥で、昔、強く抱きしめられた記憶が蘇る気がした。
けれど、その抱きしめ方は、あの頃の“恋人”への抱擁とは違っていた。
久しぶりに見つけた『置き忘れた物』に向けられる、かすかな懐かしさに過ぎなかった。
葛葉はルームシェア先の自室に入って、クマさんを棚の上にポンと置く。
彼女は今、ルームシェア先で知り合った隣人と付き合っている。
演劇部の先輩とはとっくに別れていた。
夜遅くまで笑い声が絶えない、賑やかな学生生活を送っていた。
部屋の奥から楽しげな笑い声が響く。
クマさんはただじっと、それを見ていた。
二人の背後……窓の向こうの空は、薄く冷えた灰色に見えた。
やがて雨が降り出す。
ぬいぐるみは棚の上から、静かに二人の背を見ていた。
黒い瞳の奥で、雨の光が淡く揺れた。
——おわり——