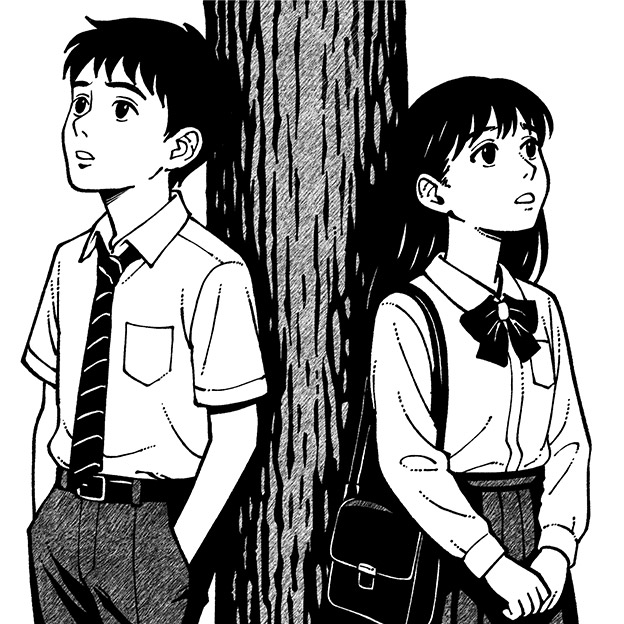学校の図書室には、いつも静かな空気が流れていた。
放課後、ほとんどの生徒が帰宅し、僕は一人で自習室にこもっていた。
図書室の隅にある自習室には、決まって誰もいない。
その広い部屋で、僕はテキストとノートを広げていた。
ある日、集中しているつもりなのに、ふと別の誰かの視線を背中に感じる瞬間があった。
振り返ると誰もいない。
気のせいか……
と、ノート下の机に目をやると、何か書かれていた。
「暇だよ」
丸みを帯びた、女の子の字。
その一行が、まるで僕に向けられたメッセージのように思えて、僕は少し驚いた。
誰かが、こんな場所で何気なく文字を残していったのだろうか。
普段なら無視するところだが、その日はどうしても気になってしまった。
僕は鉛筆でその机に返事を書いた。
「勉強はしてるよ。暇じゃないけど」
放課後の図書室、静かな時間の中で返事を待つことが少しだけ楽しく感じられた。
次の日、またその机に向かうと、手書きの文字が書かれていた。
「そんなこと言っても、楽しんでるわけじゃないんでしょ?」
その言葉にはどこか遊び心があり、僕は思わず笑ってしまった。
あの文字に込められた少しの皮肉が、また次の返事を楽しみにさせた。
その日から、毎日放課後に図書室に行き、机の上に残された返事を楽しみにしていた。
文字だけで繋がる誰かとのやり取り。
顔も名前もわからない相手だけれど、返事が書かれているとなんだか胸が高鳴る。
まるで秘密の約束を交わしているような気分になった。
「二人とも意外と顔見知りかもね。狭い学校だから」
「僕は目立たない方だからなあ」
「あはは! あなた、いつも自信なさそうだもん。でも、一歩踏み出したら変わるかもよ」
僕の、几帳面だと自分では思っている字の横に、彼女の筆圧の強い、ためらいのない線が並ぶ。
やりとりはいつも一行、二行程度で簡潔で、でもどこかしら温かみがある。
どんなに忙しい日でも、必ず放課後には机の上に返事が残されている。
相手の言葉が、次第に心に響くようになった。
—— 彼女のこと、ちゃんと知りたい。
最初はただの興味本位だった。ただの気まぐれから始まったこの文通。
でも、次第にその相手のことが気になっていった。
文字の向こうにいる彼女、もしくは彼。
もしかしたら、僕の隣に座っている誰かかもしれない。
僕はその文字を見つめながら、返事を書いた。
「君は、誰なんだろう?」
机に書かれた返事は……
「私もあなたが気になるかも。でも会うのは怖い」
その言葉に、僕は胸が苦しくなった。
僕も同じだ。会いたいと思っている。けれど、思っていた相手じゃなかったらと思うと怖い。
でも少しでも彼女の顔が見たかった。
僕は思い切って提案した。
「明日の放課後、終礼が終わったらすぐ図書室横の樹の下で……僕は待っている」
僕の心は期待と不安でいっぱいだった。
次の日、僕は樹の下で待った。時計の針がどんどん進んでいく。まるで時間が僕を試しているみたいに、一分一分が長く感じられた。
しかし、誰も来なかった。彼女は現れなかった。
どうしたんだろう?
視界の端が微妙に霞んで、ふと我に返ると、短針はもう下校時刻に近づいていた。
待ちくたびれて、自習室のいつもの机に向かったが、机の僕の字の横には返事がなかった。
次の日の放課後、いつものように丸い字でメッセージが書かれていた。
「ごめんね」
その一言に、心が締め付けられるようだった。
「どうしてこなかったの!」
これだけ書くのがやっとだった。歯がゆい一日ごとのやりとり。
「実は私、あの場にいたの」
「嘘つき! いなかったよ!!」
「あなたは気づかなかったけれど、図書室横の樹の下で私はあなたのことがわかったの」
「君がいたら気づくよ!」
「私の気持ち、わからなかった?」
意味がわからない。彼女の気持ち……どういうことだ?
彼女は毎日一言ずつ教えてくれた。
「はじめて、あなたが書いたその文字を読んだとき、私はあなたに特別なものを感じた」
「あなたと私は、同じ気持ちを持っている」
「あなたが私を想うその気持ち……私も持っていることに気づいた」
どういう意味なんだ?
返事の言葉が僕の頭の中をグルグルする。
まさか、僕と彼女はお互い好きあって……
「あなたの手が、私の言葉を書くときに少し震えたの、気づいてた?」
思いがけない返事に僕の思考は止まった。
勉強に集中していたはずの一瞬、ふっと意識が途切れて、その隙間に彼女が前に出てきた。
気づけば、僕の手が勝手に机に落書きをしていた。
それをあとから僕が読んで、返事を書いた。
僕の返事を読んだ彼女が、また僕の手を借りて返事を書く。
ずっと、そのくり返しだった。
会いたいと思っていた相手は、実は僕自身だったのだ!
「僕は自分自身に恋したというのか?」
「それが、なにか悪いの?」
その言葉は僕の胸の奥に静かに落ち、図書室の夕暮れと重なっていった。
消されることのない鉛筆の線だけが、机の上に残った。
—— おわり——